
スラブ研究センターニュース 季刊 2002 年夏号 No.90
家田 修 (センター)
スラブ研究センターは 1995 年から COE (卓越した研究拠点) に指定され、国際シンポジウム経費や外国人研究員招聘経費などを優先的に配分されてきました。 この COE 特別予算の中に短期在外研究制度があり、筆者は昨年度、この制度の利用が認められ、オックスフォード大学に半年間ほど滞在しました。 ところが、この間に新しい研究支援制度の発足が決まり、COE 制度は廃止の運命となり、COE 在外研究も筆者が最後となりました。 もちろん、筆者が最後になったからと言って、以下で制度全体を総括するつもりはないのですが、極小部局であるスラブ研究センターにとって 10 年に一度回ってくるかどうかという通常の在外研究制度に頼らず、独自にセンター研究員を海外派遣できる COE 在研は貴重な制度でした。
さて筆者が滞在したオックスフォード大学セント・アントニー校ですが、このカレッジについては、すでに数年前、センター前教授の皆川さんが滞在記をセンターニュースに書いています (2000 年 1 月号)。 そこではセント・アントニー校、そして大学街自身についての基本的な紹介がなされていますので、ここでは重複を避けて、かなり私的な体験に基づくお話をし、在研の報告に代えたいと思います。
 |
| ユーゴスラヴィア大統領コストゥニッツァ (向かって右) と専任研究員アッシュ |
|---|
セント・アントニー校には北米地域を除く世界のすべての地域について研究センターが付設され、その内の一つがロシア・東欧研究センターです。 これまでセンター長はロシア現代政治の大御所アーチー・ブラウンが長期にわたって務めてきましたが、昨年からその弟子で、英国王立国際問題研究所勤務の経験を持つアレックス・プラウダ (ロシア外交専攻) に交代しました。 プラウダはその名が示すようにスラブ系出身 (両親がチェコ人) ですが、少年時代に家族とともに英国へ移住し、学歴・経歴ともにイギリス人として歩んできたといった方が適切かもしれません。 ちなみに今のロンドン大学スラブ研究所長はポーランド出身のジョージ・コランキェヴィッチですから、くしくも東欧系の学者がイギリスのロシア東欧研究を代表する役職に並び立っている訳です。 それはさておき、プラウダは非常に柔軟かつ明晰な頭脳の持ち主で、オックスフォード大学における新しいロシア研究の顔となることは間違いありません。 ロシア東欧研究センターにはこの他にレーニン研究で知られる思索家型の研究者ロバート・サービス、そしてキャロル・レオナードというアメリカ出身のロシア経済専門家がいます。 ホームページ上はティモシ・アッシュという東欧担当の研究員もいるのですが、アッシュは同校のヨーロッパ研究センター長であり (蛇足ですが、アッシュは同校きっての論客です)、実質的にも東欧研究者とは言い難いので、スタッフから見ると、ロシア・東欧研究センターではなく、ロシア研究センターです。 という訳で、セント・アントニー校に所属する東欧専攻の大学院生は、実質的な指導を他のカレッジの東欧研究者にあおがざるを得ないのが実情です。 東欧を専門とする筆者としてもカレッジのこの実情には物足りなさを覚えたのですが、逆に、いろいろなセミナーにおいて東欧からの視点で意見を述べたり、東欧専攻の大学院生に助言を与えたりする役目が筆者に回ってくるなど、結果的に少しはこの大学院カレッジに寄与することもできたのではないかと思っています。 このセンターについていまひとつ付け加えておくべきは、センター準専任のロイ・ジャイルのことです。 彼は軍人上がりで、ロシア軍の再教育担当者として数年間ロシアに滞在した経歴の持ち主です。 彼のセンターにおける役割については不詳なのですが、オックスフォードが気に入ったので、ずっとここで暮らすことにしたと言って家も買ったそうです。 それはともかく、彼は軍事力の行使が国際政治や地域紛争の解決に対してどの程度役割を果たしうるかについて、常に明確な指標を示し、ともすると軍事力過信に走りやすい政治家達を戒める役回りを演じていました。 軍事力は紛争解決の最終的手段ではないし、なりうることもない、というのが彼の基本的姿勢なのです。
さて大学院カレッジとしてのセント・アントニー校の特色は各研究センターが独自に組織している定例セミナーとセンター横断型の特別企画セミナーの二つに集約されます。 いずれも学期 (8 週間) ごとに主題を設けて毎週一回の講演者が決められ、このセミナーが研究会と大学院教育の二つの機能を同時に果たします。 個々の講演の質は、正直なところ、玉石混淆ですが、文字通り世界中から講演者が集められ、このカレッジが世界の時事問題研究の中心的存在になっていることは一目瞭然でした。 折しも 9・11 後の世界政治の動きと合わせて研究者達がどう対応するかを間近に観察することができ、いっそうこの思いを強くしました。 政治学者、政治家、ジャーナリストなどが職業上の垣根なく大学の壇上で、テロリズムにどう対応すべきか、そもそもテロリズムとは何か、アフガンに空爆すべきか否か、軍事介入の効果はあるのか、といった現在進行中の国際問題について徹底的に議論が戦わされるのです。 もちろんこうした時事問題指向はオックスフォード大学全体に共通している訳ではなく、国際政治に特化しているセント・アントニー校の特色、さらには今の校長が外務省上がりであるという特殊事情にもよっているのでしょう。 ともあれこうした現状分析指向のカレッジが 1000 年近い学問の伝統を重んじる多くのカレッジと共存しているところにオックスフォード大学の強みがあるのだろうと思いました。 あるいは私学としてのカレッジの自立性と国立としてのユニヴァーシティの統一性という非対称的な大学設置形態が生み出す妙味と言えるのかもしれません。
筆者は滞在期間中、ロシア東欧セミナー、ヨーロッパ・セミナー、そして特別企画セミナーに出席することを日課とし、これ以外にヨーロッパ研究センターを使って行われていた週一回の大学院東欧史クラス (オックスフォード大学ではセミナーは講演形式の授業を指し、日本でいうゼミはクラスと呼ぶのが一般的なようです) にも出ていました。 セミナーはだいたい夕方 5 時から始まるので、日中はカレッジの図書館でモノグラフの執筆を行い、その後セミナーに行くというのが生活のリズムでした。 さて、東欧史クラスの担当者は聖エドモンド校所属のリチャード・クランプトン教授で、大学院生でない筆者の出席を快諾して下さいました。 この演習出席には幾つかのねらいがありました。 第一に、オックスフォード大学で東欧史が大学院生を対象にどう教えられているのか知りたかったことです。 これは筆者の務めるスラブ研究センターが 3 年前から始めた大学院教育にとって、何か得るところが必ずあると考えたからです。 第二は東欧史を専攻するイギリスの大学院生と知り合い、若手研究者の研究動向を知ることでした。 前者については、担当教員によって違いもあるのでしょうが、クランプトン教授は実に正統派でした。 まず膨大な文献リストを示し、その中から十冊程度の基本文献を読むように指示します。 そして授業では主題を決めて学生に討議させ、必要に応じて講義に近い解説を行うというやり方です。 また年三回の学期をそれぞれ両大戦間期、社会主義期、そして社会主義以後の主題に分け、これを毎年繰り返すという方式をとっています。 ですから大学院生はどの学期から取り始めても、三学期継続して聴講すれば、東欧現代史を一通り学ぶことができる訳です。 演習以外にも各学生に対して時間をとり、個別指導 (チュートリアル) を行っています。 つまり学部カレッジの方式がそのまま引き継がれている訳です。 (ちなみにクランプトン教授の文献リストにご関心をお持ちの方は個別的に筆者までご連絡下さい。 膨大なので、ここでは省かざるを得ませんでした。)
さて、クランプトン教授の演習に参加していた大学院生の大半は、と言っても全部で 10 名足らずでしたが、イギリス人ではなく、東欧ないしウクライナ、ベラルーシの出身者でした。 アメリカからの学生も二人いましたが、その内の一人は父親がポーランド系という家族関係なので、生徒は圧倒的に東欧からの留学生ということです。 唯一オックスフォード大学出身のイギリス人院生は歴史学部出身で、ハンガリーの政治倫理 (corruption) を専門にしていました。 もともとこの学生の学部時代のチューターが古代史における政治倫理の専門家だったとのことですが、新聞で報道されたハンガリーでの汚職事件がきっかけでこのテーマを選んだということです。 ハンガリーを専攻しているもう一人の大学院生はアメリカからの留学生 (ソルトレークシティ出身) で、二年間のハンガリー生活体験 (布教) が元になっているとのことでした。 さらに、このゼミ生ではなかったのですが、セント・アントニー校に所属するいま一人のハンガリー専攻の大学院生は (父親はオランダ人で、母親が英国人)、M. ラーコシというハンガリーの小スターリンと呼ばれた共産党政治家および 1950 年代を研究主題にしていました。 この学生の指導教員はオックスフォード大学にいるもう一人の東欧史、というよりむしろ中欧史の大家ロバート・エヴァンズ教授です。 この師弟、専門は東欧とはいえ、かなり違った問題関心を持っているのですが、両者に共通している点は、共にハンガリー人の配偶者に恵まれたということです。 オックスフォード大学には何十という国別ないし地域別の研究会ないし親睦会、つまり現地語で society があるのですが、おそらくハンガリー研究会は最も盛んな活動を誇っていると言ってよいでしょう。 実はこの研究会、エヴァンス夫妻の個人的な努力によって支えられており、とりわけ同夫人 (カティ) の力が大きいのです。 夫人自身も大学図書館 (ボードリアン図書館) の司書ですが、オックスフォードで夫人の (を) 知らないハンガリー関係者はいないというくらい精力を注いで会を運営しています。 会は学期中毎週一回、夜の 8 時に開催という、全く夜型人間を想定したものですが、筆者もこの会の常連となり、何か話せと言うので、日本におけるハンガリー研究に現われた「ナショナル・ヒストリー」の問題性についてしゃべりました。 さらに夫人は筆者の息子 (19 歳) のハンガリー語、そしてハンガリーでの音楽的経歴に目をつけ、小さな演奏会まで準備しました。 日本人親子に出番を作った夫人の思惑は複雑だったようです。 つまりハンガリー人でもイギリス人でもない第三国人がハンガリー語を話し、かつハンガリー文化に深く関わっている実例をハンガリー系二世・三世に示し、祖国語学習への刺激にするという意図が込められていたようなのです。 確かに、ハンガリー語にかかわらず、英語万能の時代に、当の英国で出身民族の言葉を次世代に伝えるのは容易でないようです。
筆者の関心故に、話がハンガリーに傾きすぎてしまいましたが、ハンガリーに限らず、若い世代の東欧研究者達に共通しているのは、戦後史とりわけ現状分析に関心が集中していることです。 クランプトン教授は両大戦間のブルガリア史、エヴァンズ教授は近世ハプスブルク史がそれぞれ専門ですから、なかなか指導も大変そうでした。 もっとも、そこは欧州内という地の利があり、大学院生達は奨学金や自費で現地をしばしば訪れ、実地の調査を行っています。 この辺は日本の大学院生よりも教育研究環境に恵まれていると言えるかもしれません。
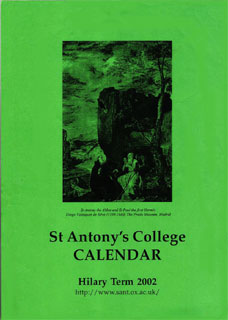 |
| セミナープログラム表紙 |
|---|
ちなみに英国の他のスラブ関連研究機関の近況について少し述べますと、まず先に触れたロンドン大学スラブ研究所は正式にはロンドン大学という大学連合に属するユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン大学 (略称 UCL) 付設スラブ東欧研究学院という長い名称になります。 UCL の傘下に入ったのは 1999 年で、これにより経営が安定したと言われていますが、同時に 500 名近い学部生を教育する学部機能も引き受けるようになりました。 いまでも 60 名の専門家を擁する世界最大のスラブ研究機関ですが、研究、大学院教育、学部教育という三つの機能すべてを満たすのは至難の業ではないかと思われます。 所長の話では研究所の場所もこれまでのセナート・ハウスから別棟に近々移転するそうです。 個人的な感想を言えば、現在のスターリン様式を思わせる巨大な建物は好みでないのですが、やはり長年あった場所から消えるとなると、どこか寂しさを覚えます。 英国にはこのスラブ研究所の他、グラスゴー大学に大きなスラブ研究機関がありますが、今回の滞在中は訪問する機会がありませんでした。 その代わり今ひとつの著名な研究機関であるバーミンガム大学ロシア・東欧研究センターには研究報告の機会を含めて二度ほど訪れました。 このセンターは北大スラブ研究センターと同程度の規模で、スタッフもロシアを専門とする専任が多く、1999 年の北大スラブ研究センター夏シンポで基調講演をした P. ハンソン氏がここの副所長です。 東欧研究では政治や社会について幅広く論文を書いている ジュディ・バットがいます。 この研究センターも研究機関の統廃合政策の影響を受け、大学内のドイツ研究センターなど文系研究センターと合同してヨーロッパ研究所をつくりました。 従って形式的には格下げになったようにも見えますが、立派な新研究棟が立ち、実質的なセンターとしての一体性も保持した訳ですから、厳しい英国の大学予算事情を考えるなら、頑張っている方だと言えるのではないでしょうか。 研究員の研究意欲も高いと思います。 ただ、もっと教育をしなさい、という圧力が大きくなっている、とハンソン氏は語っていました。
オックスフォード大学におけるカレッジの原型は修道院にあり、セント・アントニー校のように 19 世紀に始まったような新設カレッジも (大学を構成するカレッジとして認定されたのは戦後のこと) 周囲とカレッジを区切る高い塀、そしてオックス・ブリッジの代名詞とも言える緑の芝をもっています。 もっとも学部カレッジが今なお食事の時に黒のガウンを着用し、一同が定刻に食堂へと集まり、ラテン語でお祈りしてから一律の食事をとるのに対して、さすがに大学院カレッジでは時間も献立もかなり自由になっています。 しかし夜の門限は厳密に施行され、基本的な生活のあり方自体は昔ながらです。 まさに保守主義は学問だけでなく、こうした生活様式にまで徹底されています。 ところで、筆者のような研究員身分の者にとっては学期中に週二回の頻度で設定されるハイ・テーブルという夕食会が楽しみの一つでした。 ハイ・テーブルというのはもともと学生との共同の食卓において上席という意味合いで使われ始めた言葉なのでしょうが、古いカレッジでは本当に雛壇のように一段高くなっているので、上座か下座かではなく、高いか低いかという空間的な高低から来た表現かもしれません。 最近のイギリス映画「ハリー・ポッター」をご覧になった方は魔法使い学校の食事風景から雰囲気をご想像下さい。 ただしセント・アントニー校の食堂は鉄筋の新しい建物の中にあり、上座であるとか、雛壇があるわけではないので、昔ながらの雰囲気は全くありません。 さて夕食会と言っても、食事それ自体が目当てなのではなく、誰と向かい合わせになるのか、あるいは隣り合わせになるのか、この辺にハイ・テーブルの醍醐味があるのです。 先に紹介した皆川教授が滞在していた時は、英国のさる著名な王族夫妻と同席したとのことですが、そのような機会は極く希れとして、全く見知らぬ地域や分野の研究者や客人とくつろいだ雰囲気で会話を楽しみ、知人の輪が広がってゆくのは、他では得られない体験です。 このような場はオックス・ブリッジが伝統的に培い、他の大学では見られない習慣のようです。 セント・アントニー校ではその週のセミナー講演者や外来の客人がここに招待され、筆者のような客員はセミナー予定表から出席者の顔ぶれを想像し、これはという時に出席の意志を前日の昼までに知らせておくと、席が確保されるという仕組みです。 席といえば、さすがに伝統を重んじる英国らしく、ちゃんと席順があり、身分と所属期間、さらには年齢で座る場所が決められます。 そしてセント・アントニー校側出席者 (招く側) と客人側で席を向かい合わせに分けるという配慮もなされます。 客員研究員は客人側かと思ったのですが、客員は現地語でシニア・アソシエイト・メンバーと言い、つまりカレッジのメンバーと見なされているので、招く側の列に座ります。 もちろん飲食代はしっかりと徴収されます。 いま席順が厳密に決められていると書きましたが、実はそれは第一次の会食に際しての話であり、そのあと別室に移って続けられる二次会 (デザートと食後酒が供される) では自由に座ることになっています。 ただしここでは第一次会食時に隣だった者とは離れること、という原則があります。 さらに三次会がシニア・メンバー用談話室で続けられ、コーヒーと紅茶が供されます。 ここにはスコッチ類も備えられており、自由に飲むことができますが、自己申告により別料金で請求されます。 この三次にわたる飲食会の全体がハイ・テーブルになるわけですが、部屋を変えるごとに話し相手が変わり、話題も広がってゆくというのは、実に良くできた仕組みです。 日本ならさしずめ学会や研究会などの後の懇親会、その後の二次会、三次会に相当しますが、それが制度化され、しかもカレッジの中で完結するようになっているのです。 さらには研究分野を越えて様々な人と出会えるわけですから、まさに学際的この上ないわけです。 知的刺激とはまさにこういうものかと実感しました。 ハイ・テーブルという極めて独自な「出会いの場」の存在は今回のオックスフォード滞在で最も印象に残ったことの一つでした。
さて、先にカレッジは私学だと書きましたが、会計は本当に厳密で、パソコン室設置のプリンターから一枚印刷するごとにその代金が各人の会計帳簿に自動的に付加される仕組みになっています。 大学の授業料、そしてカレッジの寄宿料も高く (そもそもイギリスの物価は日本以上ですが)、庶民が子女をオックス・ブリッジのカレッジに通わせるには大変な努力が要ります。 しかし高い授業料や寄宿料もカレッジ運営財源の一部でしかなく、外からはよく分からないのですが、独自の収入源がいろいろとあるようです。 風聞ですが、それぞれのカレッジは長い歴史の中で獲得してきた資産を運用し、それが重要な財源となっていると言われます。 国はオックスフォード大学の予算増額要求に対し、カレッジの財政を透明にせよと反撃していますが、この種の駆け引きはオックスフォードの歴史と共に古いのだと思います。 オックス・ブリッジで有名なワイン蔵についても同様に長い歴史がありますが、あるセント・アントニー校専任研究員の話によりますと、オックスフォード大学のカレッジは世界有数のワイン取引量を誇り、毎年、各カレッジのワイン担当者は売り込みにくる業者が主催する試飲会に招かれるのだそうです。 いいワインを買い付け、値が上がったところで売却益を上げることもあるとのことですが、もちろん利き酒に失敗すれば、ハイ・テーブルの食卓に美味しくもないワインが出る訳です。 ともあれ、こうした「副収入」によってカレッジは数多くの教員 (フェロー) を抱えることが可能となり、この教員の数と質がオックスフォード大学特有のきめ細かい教育を保証している訳です。
セント・アントニー校の財産はフランス系の資産家による寄付が出発点になっているのですが、筆者の滞在中も、「基金を増やそう」と銘打った催しが幾度も行われました。 そうしたたゆまぬ努力により、二年ほど前、総工費 6 億円の 5 階建て新学寮が完成しました。 外観はネオ・ビクトリア調の煉瓦造りで、一回には講義室とフィットネス室が備わっています。 このネオ・ビクトリア調住居、なかなか見かけも良く、一般に新築住宅様式としても人気が高いのですが、実は幾つか問題があります。 筆者はオックスフォード到着後、事前に手配してあった市中の住宅に入居できないという非常事態になり、緊急避難的に二週間ほどこの新学寮の家族用住居 (2LDK) に滞在しました。 入居後、数日経った朝、トーストの焦げる臭いに気づいて台所にいくと、突如、寮内の火災警報がけたたましく鳴り出しました。 火災訓練の予告など受けていなかったはずだが、などといぶかっていると、入り口の呼び鈴が鳴るのです。 出てみると守衛が数人そこに立っており、早く下に降りなさいと言って、一家全員を住居から追い出しました。 玄関前に出ると他の住人達も集まっていましたが、特にあわてた様子もないので、本当の火事ではないことは分かりました。 狐につままれたような気持ちでいると、守衛達が降りてきて、筆者に向かい「あなた達の住居の火災探知器が煙を感じて警報が鳴ったのだ。これからはトーストを焦がさないように。それから、火災警報が鳴ったら、すぐに下に降りるように」と言って去っていきました。 え、あの程度の煙で警報が鳴るの、と思いましたが、朝から他の住人に迷惑をかけた以上、謝るほかありません。 「すいません」と言うと、皆微笑んで、「いつものこと」、「私もやったのよ」、「一週間に一、二回はあるから、覚悟しておいた方がいいよ」等々の応答が返ってきました。 何のことはない、寮生になるというのは、探知器の過剰な反応に慣れるということだったのです。 実際、わずか二週間の在寮中にも数回、今度は筆者のせいではなく、全員集合の警報が鳴ったのでした。 学寮を出て、市中の住居に移って数日経った頃、実はもう一度、報知器を鳴らしてしまったのです。 どうして良いか分からず、困ったと思っていると、同じ階ですぐ横の住人が駆けつけてきて、報知器のスイッチを切り、窓を全開にし、煙を追い出すという一連の作業を、手際よくやってくれたのです。 何とも人騒がせな過敏症の火災探知器だと、腹が立ったのですが、意外な効用のあることに気づいたのです。 つまり警報ベル騒ぎは、見知らぬ人に遠慮がちで人付き合いの悪いイギリス人と自然に会話を交わし、顔見知りになるまたとない機会なのです。 実際、学寮でも「全員集合」の時が新寮生との顔合わせや自己紹介の場でしたし、二度目の時も、一緒に煙を追い出す作業の中で奇妙な一体感が生まれ、これがきっかけとなって、呼びつ呼ばれつという付き合いが始ったのです。
さて、ビクトリア調の赤煉瓦というと、日本では旧制大学の建物など、古いというイメージと結びつきますが、オックスフォードの大学人達は別な意味合いで「赤煉瓦大学」という表現を用いているようです。 つまり、それは 19 世紀にできた新しい大学であり、自分たちの大学は石造りだ、という自負心と一対になっているのです。 逆に、オックスフォードの先生達は気取っているという反発も強いようですが、赤煉瓦造りの家は住み心地という点では、火災探知器は別としても、重大な欠陥があると言わざるをえません。 つまり天井と床に何らの防音対策が施されていないのが普通で、足音やテレビの音どころか、話し声までが上下で筒抜けなのです。 最近のネオ・ビクトリア調住居は内壁をコンクリートにし、防音用隙間を作るなど工夫をしているようですが、それでも不十分です。 日本のアパートやマンションもさほど自慢できる訳ではありませんが、その比ではないのです。 横壁は何とか防音できているので、何故上下にきちんと対策を講じないのか不思議です。 こればかりは、英語のヒヤリング練習になる、などと言って効用を並び立てる程、気楽ではありません。 場合によっては訴訟沙汰になるほど深刻ですし、些細な諍いは個人的体験も含めて日常茶飯です。
イギリスで人気の高いビクトリア調住居には同じ階の隣人とは親しくなり易く、上下の隣人とは対立関係が生まれ易いという「構造的」特性があるようです。 ともあれイギリス人が傍目に見てもひっそりと生活しているのは住宅構造とも関係しているのかもしれませんし、あるいは反対に、ひっそりと住むイギリス人気質が防音効果不要の家を生みだしたのかもしれません。
(つづく)