
3日間で首都での調査をほぼ終え、ラスールの車で、土曜日からいよいよ郡部を回る。最初に狙ったのは、「ダゲスタンの屋根」、ウンツクーリ郡にある、シャミールの生村ギムルィである。この村は、ダゲスタンの初代イマームであるガジ-マゴメド(シャミールは3代目)の生村でもあるから、19世紀ダゲスタン最大級の英雄を2人も輩出したことになる。シャミール自身がそうであったように、この村はアヴァール人村である。ウンツクーリ郡は、距離的にはマハチカラから遠いわけではないが、マハチカラの隣市のブイナクスクを越えたあたりから道は困難を極める。たとえば、ウンツクーリ郡に入るためには4キロのトンネルを通らなければならないが、トンネル内の道路は砂利道で穴だらけ、照明はなく真っ暗、壁面はでこぼこであり(日本の山間部でよく見る、がけ崩れ防止のために山の斜面をコンクリートで固めたのと同じである)、コンクリートの塊が時折降ってきているようだ(暗闇の中で、穴だけでなく、路上のその塊をよけながら運転しなければならない)。
ようやくギムルィ村に着くと、村長も、私たちのお目当てであったダゲスタン宗教界の大物であるラマザン・ハッジも、郡都ウンツクーリのさらに向こう側にあるカハブロソ村で行われる祭りにでかけて留守だという。カハブロソ村は、アヴァール民族詩人マフムードの生村であるが、マフムードを記念する祭りに合わせて、村に新しく建設されたバレーボール場のお披露目をしていると言う(ダゲスタンの郡部では共同体的な紐帯が強い上に、なにしろ住民が呑まないので、文化スポーツ関連の行事がやたらと多い)。さてどうするか。夕方までギムルィ村でリーダーたちが帰ってくるのを待つか、それとも「ダゲスタンの屋根」、カハブロソ村まで車で登るか? 私たちにリーダーたちの居場所を教えてくれたギムルィ村の文化会館長であるカミーロフ氏は「行こう。
ウンツクーリまでは道はまともだから」と、さかんに私たちをその気にさせる。どうも、足がなくて諦めかけていたお祭りに自分が行きたいだけではないかという感じもする。他方、ラスールは、最近ドイツから駆ってきた、舐めんばかりに可愛がっている中古のオーペルに無理はさせたくない。
結局、行こうということになり、カミーロフ氏を同乗させて出発する。ラスールが無謀な冒険に乗り出す決心をしたのは、仕事もさることながら、カハブロソ村に行く途中にある、コーカサス戦争最大の激戦地アフリゴを私に見せたいと希望したからである。まさにここで、1839年の夏、シャミール軍は自軍の数倍、約1万人のロシア軍を相手に陣を構え、1ヵ月半持ちこたえたのである。郡市を過ぎると、言われた通り、道はほぼ消滅する。民族社会学者でダゲスタンの山の中を走り回るのが商売のラスールが、車体の低い西側の車を買った理由がわからない(以前、彼はジグリに乗っていたそうだ)。地面はオーペルの車体の底を絶えず引っ掻き、跳ねた石が車体を傷つける。息を呑むような奇観絶景を楽しみつつも、面倒を引き起こした張本人としては、ゴリッと大きな音がするたびに身も細る思いである。やや脇道にそれると、アフリゴを見下ろす山の尾根に着く。アフリゴは、数百メートル上から見下ろしてもそれとわかるような切り立った小山であり、難攻不落の砦であったのも頷ける。しかし、あんなところに陣を構えて、食料と水はどうやって調達したのだろうか。
月曜日には、南部のデレベント市に向かう。ここはラスールの故郷であるため顔が利くということもあったが、宗務庁の影響が届かない南部の状況を見てみたかったのである。デレベントは、コーカサス山脈がカスピ海に向かって最もせり出した栓のような位置にある。実際、山と海の間の距離は数百メートルしかない。ギリシャ人以来、この集落・都市の名称は何度も変わったが、その多くは、「門」という言葉を含んでいた。たとえば、アラビア語の呼び名はバブ・アル・アブヴァブ(「門の中の門」)、チュルク語の呼び名はテミール・カプィ(「鉄の門」)である。これは、この地の地政学上の枢要性を表している。
考古学調査によれば、この地に集落が生まれたのは紀元前3000年頃のことらしい。しかし、都市史上の画期となったのは、5、6世紀、ササン朝下のイランが、北コーカサスからの遊牧民の侵入を防ぐために、この地の山と海の間に長城を築いたことである(こんにちでも旧市街は長城の中にすっぽり入っている)。デレベントは、文字通りの栓となったのである。石材に恵まれているため、まちには第一千年紀以来の石造建築が多数残されており、比較的新しい建物も威厳がある。今年、市庁の努力が実って、デレベントは世界遺産に指定された。
※ ※ ※
私がダゲスタンを去る日、共和国民族相が暗殺された。ラスールの奥さんは、共和国中央病院に勤めるお医者さんなので、ニュースより先に私たちはその事件について知った。この大臣は巨額な移民フォンドの運用をめぐって悪い噂が絶えない人であったらしい。「ダゲスタンでは、政治や宗教を理由に人殺しが起こることはない。ダゲスタンで人殺しが起こる理由は、たった一つしかないよ。でも見てな。マスコミでは全く別な風に言うから」と言って、ラスールはニヤニヤ笑っている。その後、キエフで見たロシアの中央テレビでは、暗殺はワハビストがやったということになっていた。もちろんこれは、第2次チェチェン戦争を正当化するためのプロパガンダである。
1998年に、当時のムフチーが兄弟・運転手もろとも爆殺された際も、アヴァール人民族主義者は、ワハビストがやったと主張した。ワハビストがやったとすれば、ムフチーは殉教者になれるからである。しかし、このテロの背景も、実のところ謎である。
さてこのダゲスタン最後の日、ラスールに頼み込んで、私は生まれて初めて火器というものを扱った。といってもピストルや猟銃ではなく、ラスールが所有する自動小銃「サイガ」である。自動小銃は引き金を引くだけで弾が出てしまうので、射撃場でも周りのお客さんからとても嫌われる。よい子は真似をしないように。極度の近視のため、ほとんど勘で撃っているのだが(長銃を構えると、視界が眼鏡の枠の外に出てしまうので眼鏡は役に立たない)、銃の性能がいいため、面白いように的の中心に当たる。一緒に射撃場に行ったラスールの長女のアイーダ嬢は、職場から休暇をもらえなかったラスールの細君に代わって、私の滞在中、私たちに料理を作ってくれたのだが、彼女もこともなげに的を打ち抜き、「ダンスと同じで、射撃はストレス解消にとても効果がありますのよ」などと言って麗しい微笑を浮かべている。ああ、なんという人におさんどんをやらせていたのかと、縮み上がったのであった。
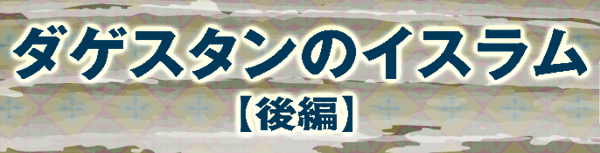
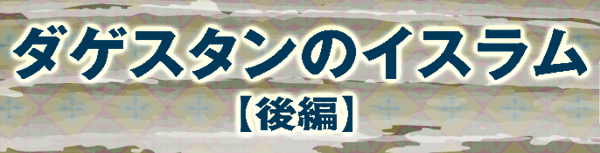
 3日間で首都での調査をほぼ終え、ラスールの車で、土曜日からいよいよ郡部を回る。最初に狙ったのは、「ダゲスタンの屋根」、ウンツクーリ郡にある、シャミールの生村ギムルィである。この村は、ダゲスタンの初代イマームであるガジ-マゴメド(シャミールは3代目)の生村でもあるから、19世紀ダゲスタン最大級の英雄を2人も輩出したことになる。シャミール自身がそうであったように、この村はアヴァール人村である。ウンツクーリ郡は、距離的にはマハチカラから遠いわけではないが、マハチカラの隣市のブイナクスクを越えたあたりから道は困難を極める。たとえば、ウンツクーリ郡に入るためには4キロのトンネルを通らなければならないが、トンネル内の道路は砂利道で穴だらけ、照明はなく真っ暗、壁面はでこぼこであり(日本の山間部でよく見る、がけ崩れ防止のために山の斜面をコンクリートで固めたのと同じである)、コンクリートの塊が時折降ってきているようだ(暗闇の中で、穴だけでなく、路上のその塊をよけながら運転しなければならない)。
3日間で首都での調査をほぼ終え、ラスールの車で、土曜日からいよいよ郡部を回る。最初に狙ったのは、「ダゲスタンの屋根」、ウンツクーリ郡にある、シャミールの生村ギムルィである。この村は、ダゲスタンの初代イマームであるガジ-マゴメド(シャミールは3代目)の生村でもあるから、19世紀ダゲスタン最大級の英雄を2人も輩出したことになる。シャミール自身がそうであったように、この村はアヴァール人村である。ウンツクーリ郡は、距離的にはマハチカラから遠いわけではないが、マハチカラの隣市のブイナクスクを越えたあたりから道は困難を極める。たとえば、ウンツクーリ郡に入るためには4キロのトンネルを通らなければならないが、トンネル内の道路は砂利道で穴だらけ、照明はなく真っ暗、壁面はでこぼこであり(日本の山間部でよく見る、がけ崩れ防止のために山の斜面をコンクリートで固めたのと同じである)、コンクリートの塊が時折降ってきているようだ(暗闇の中で、穴だけでなく、路上のその塊をよけながら運転しなければならない)。