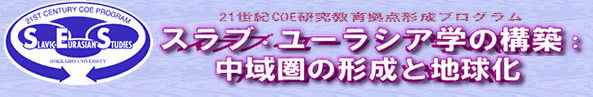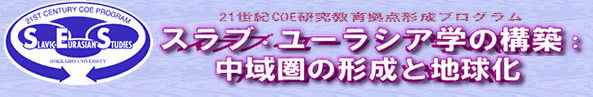|
|
|
Name
|
MAEDA Hirotake
|
 |
氏名
|
前田 弘毅
|
所属
|
スラブ研究センター |
職名
|
講師
|
学位
|
文学修士
|
現在の専門
|
コーカサス研究
|
研究内容
|
|
ユーラシア大陸の中央部に位置し、様々な文明圏やグローバル・パワーの周縁部にあって独特の多民族社会を形成
してきたコーカサス地域は、ソ連崩壊以降、世界的に大きな注目を集めている。筆者は、とりわけ中東・イスラーム世界との歴史的関係に着目して研究を進めて
きた。特に、近代イランの礎を築いたとされるサファヴィー朝(1501-1736年)における奴隷エリート(ゴラーム)の活動について、主にペルシア語と
グルジア語の文献を利用しながら、以下の論点について実例に即しつつ具体的に考察を加えてきた。
- 奴隷エリートが遊牧国家体制変革に果たした歴史的役割に関する考察
サファヴィー朝は成立時において、トルコ系部族民の武力に依存し、王族を諸地域に分封する遊牧的王権の特徴を有していたが、こうした体制下では部族間の内
紛が絶えなかった。これに対し、17世紀以降、サファヴィー朝の統治体制は相対的に安定したが、その理由は明確に説明されてこなかった。筆者はペルシア語
宮廷年代記及び地方史料をもちいて、17世紀初頭に宮廷の奴隷エリートが組織化され、彼らがトルコ系遊牧民の軍事力独占を打破し、従来の武官=トルコ系遊
牧民、文官=イラン系都市民によるトルコ・モンゴル的な2元的遊牧国家体制から、君主を頂点とするより中央集権的で垂直的な支配体制へ移行したことを明ら
かとした。
- 奴隷エリート集団の組織原理に関する考察
幼少時にイスラーム世界の外界から奴隷商人によってもたらされた奴隷エリートの組織原理は血縁によるものでなく、主人に対する服従と共に訓練を受けた仲間
意識であったと考えられてきた。サファヴィー朝の奴隷エリート内部の結合に関して、家系の継続という特徴に注目し、携わる役職や軍人、財政官などの特色が
家系ごとに継承されていた事実を指摘した。さらに、個々の奴隷エリートの経歴を整理して家系ごとに再構成することによって、この集団内部の凝集力が実際の
血縁による紐帯の維持にあったことを明らかとした。
- 奴隷エリートの出自に関する考察
従来の奴隷エリートに関する研究では彼らが出身地から隔絶された存在である点が強調されてきた。奴隷エリートの故地であるコーカサス地方のグルジア国東洋
学研究所に留学(1999-2001年)し、これまで中東研究で用いられることが少なかったグルジア語、アルメニア語史料の収集と現地の歴史研究の成果の
吸収に努めた結果、新たな史料と研究をもちいて、サファヴィー朝のグルジア出身有力奴隷エリート4家系の出自を特定し、サファヴィー朝に出仕した経緯につ
いても明らかとして、従来の奴隷エリートの定説を大幅に見直す成果を得た。
- フロンティア政策とマイノリティー・エリートに関する考察
近年イギリスで発見されたペルシア語年代記『歴史の精華』第三巻に注目し、グルジア語史料を併用することで、サファヴィー朝権力にとって「異境=フロン
ティア」たるコーカサス地域に対する施策を詳細に検討した。その結果、王朝側がコーカサスの様々な民族エリートを宮廷に抱え込むことを意図し、その際に複
雑な民族的社会的緊張と「差異」の関係を刺激して、出自に纏わるアイデンティティーの再構築が行われたことを明らかとした。一方、コーカサス出身者も積極
的にサファヴィー朝宮廷との直接的な関係を深めていった。すなわち、従来の征服・被征服といった見方の限界と、相互関係と変容による新たな歴史認識を示し
た。
以上のように、複数言語の史料を多面的に用いることにより、従来の中東・イスラーム研究やコーカサス各国の既存の歴史観に覆い隠されてきたマイノリティー
集団の歴史的なネットワークの広がりを明らかとした。中東の政治的中心から離れながら、政治エリートを輩出してきたコーカサス地域の歴史地理的特殊性は、
近現代における地域伝統と政治文化にも大きな影響を与えている。今後は、現代に至る歴史的な地域秩序形成を、民族・文化・国家アイデンティティーの問題を
検討することでより深化させ、併せて他のスラブ・ユーラシア地域との比較を念頭において研究を進めていきたいと考えている。
|
研究・教育歴
|
- 1995年 東京大学文学部東洋史学科卒業(文学士)
- 1998年 東京大学大学院人文社会系研究科修士課程修了(文学修士)
- 1999年-2001年 平和中島財団日本人奨学生・グルジア科学アカデミー東洋学研究所留学
- 2001年-2003年 日本学術振興会特別研究員(DC2・東京大学大学院人文社会系研究科)
- 2003年 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学
- 2003-2004年 日本学術振興会特別研究員(PD・東洋文庫)
- 2003-2004年 上智大学外国語学部非常勤講師
- 2004年8月- 北海道大学スラブ研究センター専任講師
|
研究業績
|
<主要論文>
- 前田弘毅「シャー・
アッバース一世の対カフカス政策:「異人」登用の実像」『史学雑誌』113編9号、2004年、1-37頁。
- 前田弘毅「『歴
史の精華』第三巻にみるサファヴィー朝の政治文化に関する予備的考察」『アジア・アフリカ言語文化研究』68号、2004年、193-213頁。
- 前田弘毅「コー
カサス展望2003-グルジアを中心に」『中央アジアを知る』ACF講座講演録集Vol.5、アジアクラブ、2004年、27-46頁。
- MAEDA
Hirotake, “On the Ethno-Social Background of Four Gholāms
families from Georgia in Safavid Iran”, Studia Iranica, 32, 2003,
Paris, pp.243-278.
- 前田弘毅「グルジア・ナショナリズムの源流:17世紀叙事詩『テイムラズとルスタヴェリの対話』の意味
すること」帯谷知可・林忠行編『スラブ・ユーラシア世界における国家とエスニシティII』、2003年、国立民族学博物館、37-44頁。
- MAEDA
Hirotake, “Hamza Mīrzā and the Caucasian Elements at the Safavid
Court: A Path towards the Reformations of Shāh ‘Abbās”, Orientalisti,
I, 2001, Tbilisi, pp.155-171.
- 前田弘毅「グ
ルジアにおける中東・イスラーム研究の現況について」『イスラム世界』56号、2001年、71-84頁。
- 前田弘毅「サ
ファヴィー朝の「ゴラーム」―「グルジア系」の場合―」『東洋学報』81巻3号、1999年、1-32頁。
- 前田弘毅「サ
ファヴィー朝期イランにおける国家体制の革新―「ゴラーム」集団台頭の歴史的意義について―」『史学雑誌』107編12号、1998年、1-38頁。
<小論等>
- 前田弘毅「グ
ルジア村の発見」岡田恵美子、北原圭一、鈴木珠里編『イランを知るための65章』明石書店、2004年、263-267頁。
- 前田弘毅「イ
ランとカフカス、日本を結ぶミッシングリンク-アルボルズとエルブルース」岡田恵美子、北原圭一、鈴木珠里編『イランを知るための65章』明石書店、
2004年、259-262頁。
- 前田弘毅「知
られざる現代史」『外交フォーラム』188号、都市出版、2004年、9頁(巻頭随筆)
- 前田弘毅「新
生グルジア:文明の交差点に光を」『朝日新聞』2004年1月26日(朝刊10面「私の視点」)
- 前田弘毅「ピ
エトロ・デッラヴァッレ『ペルシアからの手紙』」『アジアの比較文化:名著解題』岡本さえ編著、科学書院、2003年、217-220頁。
- 前田弘毅「グ
ルジア:「独立」という名の苦悩」『アジ研ワールド・トレンド』第79号、2002年、24-27頁。
- 前田弘毅「永
田雄三・羽田正著『成熟のイスラーム世界』新刊紹介」『史学雑誌』107編第7号、1998年、116-117頁。
- 前田弘毅「板
垣雄三監修『講座イスラーム世界』第1巻~第5巻新刊紹介」『史学雑誌』104編第12号、1995年、117-119頁。
|
他 -受賞歴、国際会議発表、等-
|
<2000年以降の主な発表>
- MAEDA
Hirotake, “The Forced Migrations and Reorganization of the
Regional Order in the Caucasus by Safavid Iran”, Reconstruction and
Interaction of Slavic Eurasia and Its Neighboring Worlds, Hokkaido
University (Slavic Research Center), (Sapporo, Japan), 2004 December.
- 前田弘毅「異
境」としてのカフカース:17世紀サファヴィー朝イランとグルジア」JSSEES(日本スラヴ東欧学会)第19回国際シンポジウム、東京工業大学、
2004年10月.
- 前田弘毅「奴
隷軍の諸相:サファヴィー朝の場合」日本オリエント学会第45回年次大会、金沢大学、2003年10月.
- MAEDA
Hirotake, “Shah's slave or Georgian noble? Unkonwn history of
the Georgian gholams”, The 4th International Round-Table on Safavid
Studies, University of Bamberg, (Bamberg, Germany) 2003 July.
- 前田弘毅「シャー・
アッバースの対コーカサス政策:グルジアを中心に」日本オリエント学会第44回年次大会、東北大学、2002年10月.
- MAEDA
Hirotake, “Me-17 saukunis akhlad aghmochenili sparsuli kronika
rogorts tsqaro sakartvelos istoriisatvis”, Saertashoriso konperentsia
istoriuli tsqaroebis shestsavlis aktualuri problemebi: teoriuli,
metodologiuri da kompiuteruli aspektebi”, Tbilisi State University,
(Tbilisi, Georgia) 2002 October.
- MAEDA
Hirotake, “Shah Abbas I's Policy toward the Caucasus: From the
information in the Newly Discovered Third Volume of the AFDAL
AL-TAVARIKH”, Iran and the World in the Safavid Age, The Centre for
Near and Middle Eastern Studeis, University of London (SOAS), (London,
UK) 2002 September.
- 前田弘毅「アッ
バース一世期の「ゴラーム」集団形成について:新史料『アフザル・アル・タヴァーリーフ』第3巻の記述から」日本中東学会第18回年次大会、東京大学、
2002年5月.
- MAEDA
Hirotake, “Akhali impormatsia Alaverdi Khanis shesakheb “Apdal
al-tavarikhis” mesame tomidan”, Akademiis tsevr-korespondentis,propesor
Valerian Gabashvilis dabadebidan 90 tslistavisadmi midzghvnili
sametsniero komperentsia, Institute of Oriental Studies (Tbilisi,
Georgia) 2001 October.
- MAEDA
Hirotake, “Utsnobi sparsuli tsqaro sakartvelos istoris
shesakheb: Pazlis kronika “Apzal al-tavarikh”, Martqopis brzolasadmi
midzghvnili sametsniero komperentsia, Tbilisi State University
(Tbilisi, Georgia) 2001 March.
- MAEDA
Hirotake, “Parsadan Gorgijanidzis tqveoba Shushtarshi”,
Akademiis tsevr-korespondentis,propesor Mzia Andronikashvilisadmi
midzghvnili sametsniero komperentsia, Institute of Oriental Studies
(Tbilisi, Georgia) 2000 December.
- MAEDA
Hirotake, “On the Origins of the Four Powerful Ghulam Families
in Safavid Iran”, The 7th Conference of the European Society for the
Central Asian Studies (ESCAS), University of Vienna (Vienna, Austria)
2000 September.
<学術誌編集委員会構成員(Editorial Board)>
- Kartuli Diplomatia(トビリシ大学)
- Perspektiva-XXI(グルジア科学アカデミー)
|
<--構成員一覧に戻る
|
|