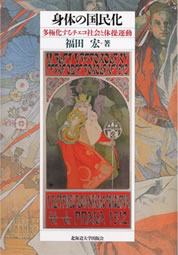荒井信
雄 4学会報告 (2)共通論題 ▼環オホーツク海圏における協力, 環日本海学会, 弘前 (2005.10)
におけるコメンテータ ▼セッション1:新ユーラシア:統合とアイデンティティー,
地域研究コンソーシアム・シンポジウム「新しい地域研究の方法を求めて:地域の形成と変容のメカニズム」, 札幌 (2005.7.9)
におけるコメンテータ (3)シンポジウム・パネル・ディスカッション ▼Session 3: Roundtable, Russian
Studies Dialogue: A Korea-Japan Perspective, Sapporo (2005.5.16)
におけるパネリスト)
|
荒井幸
康 2学術論文 (1)単著 ▼1930年代のブリヤートの言語政策:文字改革、新文章語をめぐる議論を中心に『スラヴ研究』52:145-176
(2005))
|
家田
修 1著作 (3)編著 ▼Where Are Slavic Eurasian Studies Headed in the 21st
Century? [21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集7] 75 (スラブ研究センター, 札幌,
2005) 2学術論文 (1)単著 ▼Regional Identities and Meso-Mega Area Dynamics in
Slavic Eurasia: Focused on Eastern Europe (21st Century COE Program
Slavic Eurasian Studies No. 7, Emerging Meso-Areas in the Former
Socialist Countries: Histories Revived or Improvised?, 19-41,
SRC,
Sapporo, 2005)(同タイトルで次の雑誌に転載:Central
European Political Science Review,
5(1):6-26, Budapest, 2005) ▼The Hungarian Status Law and Slovak
Acceptance (A. Duleba & T. Hayashi, eds., Regional Integration in
the East and West: Challenges and Responses, 93-105, SFAS/SRC,
Bratislava/Sapporo, 2005)4学会報告 (2)共通論題 ▼Meso-Mega Area Dynamics in
Slavic Eurasia: A Conceptual Approach to the Changing Post-communist
Countries, AAASS年次大会, Salt Lake City (2005.11.5)▼セッション7: 領域の国民化と国民の領域化,
スラブ研究センター2005年度冬期国際シンポジウム「中・東欧の地域:過去と現在」, 札幌 (2005.12.16)
におけるコメンテータ (3)シンポジウム・パネル・ディスカッション ▼Session 3: Roundtable, Russian
Studies Dialogue: A Korea-Japan Perspective, Sapporo (2005.5.16)
におけるパネリスト ▼Emerging East European Meso-area in Post-communist Slavic
Eurasia, ICCEES (International Council for Central and East European
Studies) 世界大会, Berlin (2005.7.28) におけるコメンテータ (5)自由論題 ▼Meso-area
Dynamics and Regional Identities: A New Approach to Slavic Eurasian
Studies, AAASS年次大会, Salt Lake City (2005.11.6)
|
岩下明
裕 1著作 (1)単著 ▼『北方領土問題:4でも0でも、2でもなく』264 (中公新書,
2005) (2)共著 ▼現地報告:中国と中央アジア-接触地域の現場検証, 39-72; 中・ロ国境問題の最終決着に関する覚え書, 73-81
(岩下明裕編『ユーラシア国境政治:ロシア・中国・中央アジア』[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集8]
スラブ研究センター, 札幌, 2005) (3)編著 ▼21st
Century COE Program Slavic Eurasian
Studies No. 6-1, Siberia and the Russian Far East in the 21st Century:
Partners in the “Community of Asia”: Crossroads in Northeast Asia,
x+117 (SRC, Sapporo, 2005) ▼(Д. Кривцовと共編) Взгляд вне рамок старых
проблем: опыт российско-китайского пограничного сотрудничества
[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集6] 80 (スラブ研究センター, 札幌,
2005) ▼『ユーラシア国境政治:ロシア・中国・中央アジア』[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集8] 81
(スラブ研究センター, 札幌, 2005) 2学術論文 (1)単著 ▼Вокруг проблемы
российско-китайской
границы, Мировая экономика и
международные отношения, 2:97-104
(2005)▼Вокруг проблемы российско-китайской границы, Казахстан в
глобальных процессах, 1:98-109 (2005)▼An Inquiry for New
Thinking on
the Border Dispute: Backgrounds of “Historic Success” for the
Sino-Russian Negotiations (21st
Century COE Program Slavic Eurasian
Studies No. 6-1, Siberia and the Russian Far East in the 21st Century:
Partners in the “Community of Asia”: Crossroads in Northeast Asia,
95-114, SRC, Sapporo, 2005) ▼The Shanghai Cooperation Organization and
an Emerging Security System in Eurasia (A. Duleba & T. Hayashi,
eds., Regional Integration in the
East and West: Challenges and
Responses, 41-49, SFAS/SRC, Bratislava/Sapporo,
2005) ▼中・ロ国境問題はいかにして解決されたのか?『法政研究』(九州大学) 71(4):597-614 ▼Опыт
российско-китайских пограничных переговоров: применим ли он к
территориальному вопросу между Россией и Японией? (Взгляд вне рамок
старых проблем: опыт российско-китайского пограничного сотрудничества
[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集6] 67-80 (スラブ研究センター, 札幌,
2005) 3その他の業績 (4)その他 ▼北方領土上陸記『スラブ研究センターニュース』103
(2005.11)4学会報告 (4)シンポジウムのオーガナイザー ▼日本国際学会部会「アジア・ユーラシアの国境問題を考える」, 札幌
(2005.11.20) のオーガナイザー兼コメンテータ (5)自由論題 ▼A New Era of Eurasian
Cooperation: Beyond the Sino-Soviet Border Disputes, AAASS年次大会, Salt
Lake City (2005.11.6)
|
宇山智
彦 1著作 (3)編著 ▼(小松久男・梅村坦・帯谷知可・堀川徹と共編)『中央ユーラシアを知る事典』626 (平凡社,
2005) 2学術論文 (1)単著 ▼Взгляды царских генералов на
кочевников и их
воинственность: По поводу неосуществленного плана о сформировании
конной милиции в Туркестане (М.Х. Абусеитова, ред., Урбанизация и
номадизм в Центральной Азии: история и проблемы, 194-209,
Дайк-Пресс,
Алматы, 2005) ▼旧ソ連ムスリム地域における「民族史」の創造:その特殊性・近代性・普遍性
(酒井啓子・臼杵陽編『イスラーム地域の国家とナショナリズム (イスラーム地域研究叢書⑤)』55-78, 東京大学出版会,
2005) 3その他の業績 (1)研究ノート等 ▼第2ラウンドを迎えたCIS諸国の政治変動:「革命」の誘因と阻害要因『国際問題』544:42-
46 (2005) (4)その他 ▼ウズベキスタン議会選挙監視体験記『スラブ研究センターニュース』101
(2005.5) ▼「異族人」「コレニザーツィヤ」「地震」「第2次世界大戦」「帝政ロシア地方統治規程」など66項目
(小松久男他編『中央ユーラシアを知る事典』平凡社, 2005)▼第二ラウンドに入った中央ユーラシアの変動:クルグズスタン
(キルギス)・ウズベキスタン情勢によせて『月刊百科』513:2-5 (2005) ▼座談会:中央アジアの最新情勢
(岩下明裕編『ユーラシア国境政治:ロシア・中国・中央アジア』[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集8]13-16,
スラブ研究センター, 札幌,
2005) 4学会報告 (2)共通論題▼セッション5:個別主義の帝国:中央アジアにおけるロシアのキリスト教化・兵役政策,
スラブ研究センター2005年度夏期国際シンポジウム「中央ユーラシアの地域的・超域的ダイナミズム:帝国、イスラーム、政治」, 札幌
(2005.7.7-9) ▼Spatial Redifinitions of Slavic Eurasian Territories,
AAASS年次大会, Salt Lake City (2005.11.6) におけるコメンテータ ▼クルグズスタン (キルギス)
の革命:革命のカーニバル性と不透明な政治構造の維持, 日本国際政治学会2005年度研究大会, 札幌 (2005.11.18) ▼セッション7:
領域の国民化と国民の領域化, スラブ研究センター2005年度冬期国際シンポジウム「中・東欧の地域:過去と現在」, 札幌
(2005.12.14-16)
におけるコメンテータ (3)シンポジウム、パネル・ディスカッション ▼特別パネルディスカッション「新時代におけるカザフスタンのアイデンティティー
と日本・カザフスタン関係」, ロシア・東欧学会2005年度大会, 福岡 (2005.10.16)
におけるコメンテータ (4)シンポジウムのオーガナイザー ▼地域研究コンソーシアム・シンポジウム「新しい地域研究の方法を求めて:地域の形成と変容
のメカニズム」, 札幌 (2005.7.9) ▼中央アジア研究会シンポジウム「中央ユーラシア研究の新地平」, 東京 (2005.7.10-11)
|
帯谷知
可 1著作 (3)編著 ▼(小松久男・梅村坦・宇山智彦・堀川徹と共編)『中央ユーラシアを知る事典』626 (平凡社,
2005) 2学術論文 (1)単著 ▼英雄の復活:現代ウズベキスタン・ナショナリズムのなかのティムール
(酒井啓子・臼杵陽編『イスラーム地域の国家とナショナリズム』[イスラーム地域研究叢書(5)]185-212, 東京大学出版会,
2005) ▼オストロウーモフの見たロシア領トルキスタン『ロシア史研究』76:15-27 (2005) 3その他の業績 (2)書評 ▼Arne
Haugen, The Establishment of
National Republics in Soviet Central Asia,
New York: Palgrave Macmillan, 2003, x+276 pp.『アジア経済』46(11/12):156-160
(2005) (4)その他 ▼「地域研究資料の新地平:特集にあたって」「中央アジア地域研究希少資料デジタル化の試み」『地域研究』7(1):153
-155; 185-195 (2005) ▼ブタ (異文化を学ぶ:生きものをめぐって8)『毎日新聞』夕刊
(2005.7.27) ▼旧ソ連中央アジアの国境:20世紀の歴史と現在『しゃりばり』284:54-58 (2005)▼中央アジア
(『imidas2006』444-449, 集英社, 2005) ▼「アーリム・ハン」など63項目
(小松久男他編『中央ユーラシアを知る事典』平凡社, 2005) ▼「ホップ、マイリ」:ウズベク流処世術の機微『月刊みんぱく』29(4):15
(2005) 4学会報告 (2)共通論題 ▼セッション1:中央ユーラシアの近代知識人,
スラブ研究センター2005年度夏期国際シンポジウム「中央ユーラシアの地域的・超域的ダイナミズム:帝国、イスラーム、政治」, 札幌
(2005.7.7-9) におけるコメンテータ
|
| 後藤正
憲 2学術論文 (1)単著 ▼Чувство страха перед «киреметью» и
представление о
«священном» у чувашей в конце XIX века (Ю.П. Смирнов, ред., Аграрный
строй среднего поволжья в этническом измерении, 337-346, Москва,
2005) 4学会報告 (3)シンポジウム、パネル・ディスカッション ▼Святость и
обмен: письма М. Сеспеля
к А.А. Червяковой и молитва традиционных обрядов, Международная
научно-практическая конференция «Гуманитарные науки в истории и
современном развитии общества», Чувашский научный институт гуманитарных
наук, Чебоксары (2005.11.29) |
斎藤元
秀 1著作 (2)共著 ▼ロシア外交の部分を分担執筆, 123-127
(平和・安全保障研究所編『アジアの安全保障、2005-2006年』朝雲出版社,
2005) 2学術論文 (1)単著 ▼グローバリゼーション時代のロシアのアジア太平洋政策
(滝田賢治編『グローバル化とアジアの現実』267-292, 中央大学出版部, 2005.3) ▼日中競合時代のプーチンの対日政策と北方領土問題
(上) (下)『東亜』451:70-77; 452:72-82
(2005) ▼ロシアの国際環境とプーチン外交『外交フォーラム』199:27-33
(2005.2) ▼「9・11」以後のプーチン外交『ユーラシア研究』32:39-46
(2005.5)▼旧ソ連地域と大国の関係『国際問題』544:13-25
(2005.7) ▼ロシアの外交政策と中国ファクター『ロシア・東欧ファイル』, 1-3
(2005.11.8) ▼プーチン政権の対日政策を検証『世界週報』86(45):10-13
(2005.11.29) 4学会報告 (3)シンポジウム ▼分科会B-5ロシア東欧I, 日本国際政治学会, 札幌 (2005.11.18)
におけるコメンテータ
|
佐々木
史郎 2学術論文 (1)単著 ▼ニヴヒ(綾部恒夫監修、末成道男・曽士才編『ファーストピープル』第1巻, 66-86, 明石書店,
2005) ▼「サマギールの来歴」「アムール川流域における先住民族ナーナイ(ゴリド)の集落配置とその規模」「シベリア・極東ロシア先住諸民族のシカ
猟:フィールドノートから」(大貫静夫・佐藤宏之編『ロシア極東の民族考古学:温帯森林漁猟民の居住と生業』77-99; 233-262;
295-315, 六一書房, 2005) ▼ツンドラ地帯におけるトナカイ遊牧の成立過程:帝政ロシア期にネネツとチュクチが選んだ生き残り戦略
(松原正毅・小長谷有紀・楊海英編『ユーラシア草原からのメッセージ:遊牧研究の最前線』339-370, 平凡社,
2005) ▼極東ロシア、アムール川の先住民族 (岸上伸啓編『世界の食文化⑳ 極北』23-77, 農山漁村文化協会,
2005) ▼ロシア極東地域における先住民企業の生き残り戦略:社会主義時代とポスト社会主義時代の北方先住民族
(本田俊和・大村敬一・葛野浩昭編『文化人類学研究:先住民の世界』141-168, 放送大学教育振興会,
2005) ▼山丹交易と蝦夷地・日本海域 (長谷川成一・千田嘉博編『日本海域歴史大系』第4巻近世Ⅰ, 251-278, 精文堂出版,
2005) ▼北東アジアの河川、海上交通とその拠点:「満洲仮府」デレンの繁栄 (歴史学研究会編『港町の世界史』11-47, 青木書店,
2005) 3その他の業績 (4)その他 ▼第2セッション・コメント(1)(瀬川昌久編『中国のエスニシティ』124-130,
東北アジア研究センター, 2005) ▼山丹交易におけるアイヌの役割
(『アイヌの歴史:「周辺」との交易・交流』[国際日本学シンポジウム報告書]67-77, 法政大学国際日本学研究所,
2005) 4学会報告 (2)共通論題 ▼ポスト社会主義時代の北方人類学,
日本文化人類学会第39回研究大会特別シンポジウム「北方研究から見える人類学の今日的課題」, 札幌 (2005.5.21)
|
志摩園
子 2学術論文 (1)単著 ▼戦間期の日本-ラトヴィヤ関係の考察(1)外交関係の始まり『学苑・人間社会学部紀要』772:89-96
(2005.2) ▼ラトヴィヤにおける民族・国家の形成『歴史評論』665:42-53
(2005.9) ▼『ラトヴィヤ共和国の成立と地域協力:国民国家の役割と限界に関する考察』平成15~16年度科研費補助金 (基盤研究(c)②)
研究成果報告書 (2005.12) 4学会報告 (2)共通論題 ▼セッション4:「バルト諸国」の諸相と地政学的多様性,
スラブ研究センター2005年度冬期国際シンポジウム「中・東欧の地域:過去と現在」, 札幌 (2005.12.14-16)
(3)シンポジウム ▼The Formation of Republic of Latvia 1917-1920: From the
Aspect of History of International Relations, 6th Conference on
Baltic Studies in Europe, Association for the Advancement of the Baltic
Studies, Valmiera, Latvia (2005.6.17-19) ▼国際シンポジウム「越境広域経営と地域主義」,
環日本海学会第11回研究大会「越境広域のグランドデザイン構築:環日本海(東海)地域の平和と相互交流促進の展望」,弘前(2005.10.1-2)に
おけるパネリスト
|
仙石
学 2学術論文 (1)単著 ▼中東欧諸国の政策規定要因分析試論:チェコとポーランドの環境政策を題材として『ロシア・東欧研究
(ロシア・東欧学会年報2004年版)』33:16-25
(2005) 3その他の業績 (1)研究ノート等 ▼ポーランドから見たアメリカ:2国間関係のみでは見えないもの『環』24:134-139
(2006.1)
|
高橋淸
治 2学術論文 (1)単著 ▼ズヴャギンツェフの『帰還』について『スラヴ文化研究』4:81-89 (2005.3)
|
田畑伸
一郎 2学術論文 (2)共著 ▼(M. Kuboniwa, N. Ustinovaと) How Large Is the Oil and
Gas Sector of Russia? A Research Report, Eurasian Geography and
Economics, 46(1):68-76 (2005) 3その他の業績 (1)研究ノート ▼(S. Ohtsuと) Pension
Reforms in Russia [PIE Discussion Paper Series, No. 262], 27
(Institute
of Economic Research, Hitotsubashi University, 2005) (4)その他 ▼Russia’s
Economic Integration with CIS Countries
(『ロシアの経済改革に関する調査報告書』〈平成16年度内閣府委託調査〉51-61, 日本総合研究所,
2005) 4学会報告 (2)共通論題 ▼(S. Ohtsuと) Pension Reforms in Russia,
International Workshop on Economics of Intergenerational Equity in
Transition Economies, 国立 (2005.3.10) ▼Russia’s Economic Integration
with CIS Countries, Symposium on the Russian Economy: Energy Sector and
Economic Partnership Issues in Russia, 東京 (2005.3.30) ▼“Oil and Gas
Export Revenues and Their Influence on Economic Growth of Russia, ”
ICCEES 第7回世界大会, Berlin (2005.7.30) ▼The Influence of High Oil Prices on
Russia’s GDP Growth, AAASS年次大会, Salt Lake City (2005.11.4)営
|
兎内勇
津流 2学術論文 (1)単著 ▼NII総合目録データベースにおける著者名典拠ファイルの形成過程『大学図書館研究』73:1-14
(2005.3) 3その他の業績 (4)その他 ▼中国刊行ロシア語出版物目録稿 補遺 (1)
総合目録新出分『ロシアの中のアジア/アジアの中のロシア研究会通信』9:10-14 (2005.5) ▼中国刊行ロシア語出版物目録稿 補遺
(2) 東洋文庫篇『ロシアの中のアジア/アジアの中のロシア研究会通信』9:15-24 (2005.5) ▼中国刊行ロシア語出版物目録稿 補遺
(3) 早稲田大学図書館篇『ロシアの中のアジア/アジアの中のロシア研究会通信』10:12-20
(2005.9) ▼サハリン郷土誌ビュレティン総目次 (2) 1995-1999『北海道・東北史研究』2:74-93
(2005.12) 4学会報告 (2)共通論題 ▼地域研究情報資源確保のために:ロシア・東欧関係資料の分布状況から考える,
地域研究コンソーシアム情報資源共有化・地域情報学合同研究会, 京都大学東南アジア研究所 (2005.12.5)
|
林 忠
行 1著作 (3)編著 ▼(A. Dulebaと) Regional
Integration in the East and West:
Challenges and Responses, 250 (SFAS/SRC, Bratislava/Sapporo,
2005) 2学術論文 (1)単著 ▼EU Enlargement and Euroscepticism in Central and
Eastern Europe: The ODS in the Czech Party System (A. Duleba & T.
Hayashi, eds., Regional Integration
in the East and West: Challenges
and Responses, 75-84, SFAS/SRC, Bratislava/Sapporo,
2005) ▼東中欧諸国と米国の単独主義:イラク戦争への対応を事例に『ロシア・東欧学会年報』33:47-58
(2005) 3その他の業績 (4)その他 ▼日本の外で「固有の領土」論は説得力をもつのか:欧州戦後史の中で考える『しゃりばり』283:36-
39 (2005)4学会報告 (2)共通論題 ▼セッション3: マサリクの「中欧」もしくは「東欧」:第一次世界大戦期の言説から,
スラブ研究センター2005年度冬期国際シンポジウム「中・東欧の地域:過去と現在」, 札幌
(2005.12.14-16) (3)シンポジウム・パネル・ディスカッション ▼Session 3: Roundtable, Russian
Studies Dialogue: A Korea-Japan Perspective, Sapporo
(5.16.2005)におけるパネリスト (4)シンポジウムのオーガナイザー ▼日本国際政治学会2005年度研究大会, 札幌
(2005.11.18-20) 実行委員長
|
原 暉
之 2学術論文 (1)単著 ▼巨視の歴史と微視の歴史:『アムール現地総合調査叢書』(1911~1913)
を手がかりとして『ロシア史研究』76:50-66
(2005.5) 3その他の業績 (1)研究ノート等 ▼開拓使の浦潮見本市顛末『外交フォーラム』199:56-58
(2005.2) (4)その他 ▼鈴川正久氏を偲んで『スラブ研究センターニュース』100
(2005.2) 4学会報告 (2)共通論題▼アジア海域史とロシア極東, 2005年度ロシア史研究会大会 (2005.10.22)
におけるコメンテータ (4)シンポジウムのオーガナイザー ▼日本とロシアの研究者の目から見るサハリン・樺太の歴史, サハリン国立大学
(2005.11.1-2) のオーガナイザー (5)自由論題 ▼日本におけるサハリン島民、1905年,
日本とロシアの研究者の目から見るサハリン・樺太の歴史, サハリン国立大学 (2005.11.1-2)
|
福田
宏 4学会報告 (5)自由論題 ▼チェコ体操運動における「公的なるもの」の変容:ソコル体操協会の機関誌に見る身体の国民化,
日本西洋史学会第55回大会, 神戸 (2005)
|
藤森信
吉 2学術論文 (1)単著 ▼2004年ウクライナ大統領選挙:政権交代がもたらすもの『ロシア東欧貿易調査月報』4月号:1-22
(2005) ▼オレンジ革命への道:ウクライナ民主化15年『国際問題』7月号:47-54 (2005) ▼Ukrainian Gas
Traders, Domestic Clans and Russian Factors: A Test Case for Meso-Mega
Area Dynamics (21st Century COE
Program Slavic Eurasian Studies No. 7,
Emerging Meso-Areas in the Former Socialist Countries: Histories
Revived or Improvised?, 113-136, SRC, Sapporo,
2005)3その他の業績 (4)その他 ▼ドネツクで考えたこと『スラブ研究センターニュース』100
(2005.2) 4学会報告 (3)シンポジウム ▼セッション1:パイプラインと中域圏:ウクライナ・ロシアの場合,
地域研究コンソーシアム・シンポジウム「新しい地域研究の方法を求めて:地域の形成と変容のメカニズム」, 札幌
(2005.7.9) ▼ウクライナの『オレンジ革命』は民主化革命なのか, 部会2:旧ソ連諸国における「民主化革命」の三国比較,
日本国際政治学会, 札幌 (2005.11.18)
|
前田弘
毅 2学術論文 (1)単著 ▼グルジア「バラ革命」:元祖民主革命が成就するまで『国際問題』544:55-62
(2005) 3その他の業績 (1)研究ノート等 ▼(玄承洙と解説) チェチェン紛争の現在
(ヴィアチェスラフ・アヴェツキー著、萩谷良訳『チェチェン』[文庫クセジュ890]171-175, 白水社,
2005) ▼グルジアの文書館事情『現代史研究』51:91-96
(2005) ▼国境と民族:コーカサスの歴史から考える『しゃりばり』283:40-45 (2005) ▼Rostom-Khan
Saakadze da misi ojakhi (Akhlo
Aghmosavleti da Sakartvelo, IV, 33-35
[in Georgian, with English summary p.324], Tbilisi,
2005) (4)その他 ▼二つの場所:2004年秋グルジア訪問記『スラブ研究センターニュース』100
(2005.2) ▼「イスファハーン」「シャー」「シャー・アッバース」の項目 (黒田日出男編『歴史学事典第12巻 王と国家』弘文堂,
2005) ▼「アジャリア (自治共和国) [現状]」「グルジア
(人)」「グルジア語」「サアカシュヴィリ」「シェヴァルドナゼ」「チャフチャヴァゼ」「ルスタヴェリ」の項目
(小松久男他編『中央ユーラシアを知る事典』平凡社, 2005) ▼グルジアの歴史と現状について『学習院大学人文科学研究所報2004年度版』,
45-46 (2005) 4学会報告 (2)共通論題 ▼セッション4:イスラーム復興:国境を越えた動きか、国内問題か,
スラブ研究センター2005年度夏期国際シンポジウム「中央ユーラシアの地域的・超域的ダイナミズム:帝国、イスラーム、政治」, 札幌
(2005.7.7-9) におけるコメンテータ ▼グルジアのバラ革命:「革命」にみる連続性, 日本国際政治学会2005年度研究大会, 札幌
(2005.11.18) (3)シンポジウム・パネル・ディスカッション ▼Session 3: Roundtable, Russian
Studies Dialogue: A Korea-Japan Perspective, 札幌 (5.16.2005) におけるパネリスト
|
松里公
孝 1著作 (3)編著 ▼21st Century COE Program
Slavic Eurasian Studies No. 7,
Emerging Meso-Areas in the Former Socialist Countries: Histories
Revived or Improvised?, 415 (SRC, Sapporo, 2005)▼21st Century COE
Program Slavic Eurasian Studies No. 8, Социальная
трансформация и
межэтнические отношения на Правобережной Украине 19 - начало 20 вв.,
221 (Moscow, 2005) 2学術論文 (1)単著 ▼Из комиссаров
антиполонизма в
просветителей деревни: мировые посредники на Правобережной Украине
(1861-1917 гг.), 175-221 (M. Kimitaka, ed., 21st Century COE
Program
Slavic Eurasian Studies No. 8, Социальная
трансформация и межэтнические
отношения на Правобережной Украине 19 - начало 20 вв., SRC,
Sapporo,
2005) ▼Semi-presidentialism in Ukraine: Institutionalist Centrism in
Rampant Clan Politics, Demokratizatsiya,
13(1):45-58
(2005) ▼地域研究史学とロシア帝国への空間的アプローチ:19世紀の大オレンブルクにおける行政区画改革『ロシア史研究』64:38-49
(2005) (2)共著 ▼(M. Ibragimovと) Alien but Loyal: Reasons for the
“Unstable Stability” of Dagestan, an Outpost of Slavic Eurasia (21st
Century COE Program Slavic Eurasian Studies No. 7, Emerging Meso-Areas
in the Former Socialist Countries: Histories Revived or Improvised?,
221-244, SRC, Sapporo, 2005)(若干短縮した露語版は次に公刊:Чужой, но
лояльный: причины
«нестабильной стабильности» в Дагестане, Полис, 3:102-115
(2005)) ▼(M.
Ibragimovと) Islamic Politics at the Subregional Level of Dagestan:
Tariqa Brotherhoods, Ethnicities, Localism and the Spiritual Board, Europe-Asia Studies,
57(5):753-779
(2005)(若干短縮したポーランド語版は次に公刊:Islam w Dagestanie: Bractwa religijne,
etniczność, lokalizm i zarząd duchowy, Arcana, 66:77-91
(2005)) 3その他の業績 (2)書評 ▼James W. Heinzen, Inventing a Soviet
Countryside: State Power and the Transformation of Rural Russia
1917-1929 (University of Pittsburgh Press, 2004), The Russian Review,
64(1):148-149 (2005) (4)その他 ▼学術雑誌を国際化する方法『スラブ研究センターニュース』100
(2005.2) ▼Russian Imperiology and Area Studies (Impressions on the
ICCEES Berlin Congress), Ab Imperio,
3:443-445
(2005) 4学会報告 (2)共通論題 ▼Ислам как стабилизирующий фактор
общества: опыт
Дагестана, Татарстана и Башкортостана, Second International
Symposium
on “Islamic Civilization in Volga-Ural Region, ” Kazan
(2005.6.24-26) ▼Managing the Space: The Territorial Reforms in Great
Orenburg in the Mid-Nineteenth Century, ICCEES世界大会, Berlin
(2005.7.25-31) ▼セッション6: 失われた歴史と領域認識,
スラブ研究センター2005年度冬期国際シンポジウム「中・東欧の地域:過去と現在」, 札幌 (2005.12.14-16)
におけるコメンテータ ▼Differing Dynamics of Semipresidentialism across
Euro/Eurasian Borders: Ukraine, Lithuania, Poland, Moldova and Armenia,
AAASS年次大会, Salt Lake City (2005.11.6)
|
毛利公
美 2学術論文 (1)単著 ▼境界を見つめる目:ナボコフのロシア語作品をめぐって(学位論文), 東京大学大学院人文社会系研究科
(2005.3) 3その他の業績 (1)研究ノート等▼(資料)(ボブロフ・アレクサンドル、越野剛、宮野裕、佐光伸一との共著)
東方の知られざる人々の物語『スラヴ研究』52:261-280
(2005) (3)翻訳 ▼ジンヌル・ウラクシン「一口話集」『新潮』(創刊1200号記念特別号), 68-73
(2005.1) (4)その他 ▼(翻訳、構成)「映画『太陽』と昭和天皇像をめぐって」特別対談、A.ソクーロフ×沼野充義『新潮』,
183-197 (2005.10)4学会報告 (2)共通論題 ▼Меж ностальгическим
прошлым и жестокой
реальностью: использование фотографии в литературе русской эмиграции
20-х годов, Международная конференция «Владимир Набоков и литература
русской эмиграции» Международное Набоковское Общество,
Санкт-Петербург (2005.7.21) (3)シンポジウム ▼亡命作家と越境,
公開シンポジウム「『国』という枠を離れて」,
山形 (2005.10.29)
|
望月哲
男 1著作 (1)単著 ▼『ドストエフスキー・カフェ:現代ロシアの文学事情』[ユーラシア・ブックレットNo. 81] 63 (東洋書店,
2005) (3)編著 ▼21st Century COE Program
Slavic Eurasian Studies No. 6-2,
Siberia and the Russian Far East in the 21st Century: Partners in the
“Community of Asia”: Chekhov and Sakhalin, xii+79 (SRC, Sapporo,
2005) ▼『現代文芸研究のフロンティア (VII)』[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集9] 196
(スラブ研究センター, 札幌,
2005) ▼(越野剛と)『19世紀ロシア文学という現在』[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集10] 130
(スラブ研究センター, 札幌,
2005) 2学術論文 (1)単著 ▼19世紀ロシア文学におけるイエズス会のイメージ:『カラマーゾフの兄弟』読解へのステップ
(『19世紀ロシア文学という現在』[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集10] 33-52, スラブ研究センター,
札幌, 2005) (2)共著 ▼(福間加容と) ソローキンと絵画:小説『ロマン』と19世紀ロシア美術 (『現代文芸研究のフロンティア
(VII)』[21世紀COEプログラム「スラブ・ユーラシア学の構築」研究報告集9] 41-68, スラブ研究センター, 札幌,
2005) 4学会報告 (2)共通論題 ▼セッション5: 文学・歴史の想像における空間と領域性,
スラブ研究センター2005年度冬期国際シンポジウム「中・東欧の地域:過去と現在」, 札幌 (2005.12.14-16) におけるコメンテータ)
|
山下祥
子 3その他の業績 (4)その他 ▼Хорошая...?『スラブ研究センターニュース』102
(2005.8))
|
山村理
人 3その他の業績 (4)その他 ▼ロシアの穀物輸出国への転換:その背景と展望『商品市況研究』2005年夏季特集号:3
(2005.8) 4学会報告 (3)シンポジウム ▼中央アジア諸国における土地改革:農地「私有化」をめぐって,
国際シンポジウム「モンゴル遊牧社会と土地所有:体制移行国における土地私有化の比較研究, 名古屋大学法政国際教育協力研究センター, 名古屋
(2005.9.17-18) ▼コンファレンス「20世紀ロシア農民史研究」, 東京大学経済学研究科 (2005.11.13-14)
における司会とコメンテータ
|