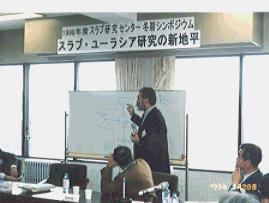
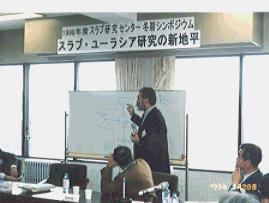
|
| 第2セッションのようす |
昨年の冬期研究報告会は平成7年度から3年間続いた重点領域研究「スラブ・ユーラシアの変動」の研究成果を公表し、総括する場と位置づけられましたが、今年度の冬期シンポジウムはテーマを「スラブ・ユーラシア研究の新地平」と定め、領域研究成果を踏まえてより発展させた研究報告が今年度の特徴となりました。なかでも、今年度文部省科学研究費助成金をえて研究成果を報告した、「ロシアの地域経済研究」(研究代表者・田畑伸一郎)、「サハリン州における持続可能な経済発展と環境保全」(研究代表者・村上隆)、「民族共和国のエリート研究」(研究代表者・松里公孝)、「20世紀ロシア文学と身体」(研究代表者・望月哲男)などが領域研究を数歩進めた研究となっていました。当シンポジウムでは、その他、若手研究者を中心とした「中央アジアの民族文化」、歴史研究に新たな展望を持たせた「ロシア農民史」や「東欧社会史」、それに題材としては新味はありませんが萌芽的研究に属する「ロシア・ソ連の権力構造」についての報告がありました。更に、スラブ研究センターで開催されるシンポジウムが年毎に国際化され、今年度の冬期シンポジウムもその例に漏れず外国人研究員によるロシア史やロシア現代政治に関するセッションが3つほど組まれました。
今後、スラブ研究センターの研究分野が益々多様化し、実証研究を通して理論化する傾向があります。従って、シンポジウムの報告内容がアカデミズムの点からみてそれなりに意義あるものであるのは疑いありませんが、他面、研究分野が雑多で、若干まとまりのないシンポジウムという印象を与えかねません。今後のシンポジウムでは、あるテーマに特化し、それを中心にして議論を展開させることも企画の一つとして視野に入れています。[皆川]
本年度のセンター公開講座は「北方ユーラシアの開発と環境」をテーマとして下記の日程で行われます。近年、北方ユーラシアでは森林の破壊が進み、大気汚染も深刻になっています。オホーツク海では史上初めて海洋石油、天然ガス開発が始まろうとしています。この地域ではいままさに「開発と環境」の二律背反の問題が問われています。今回は自然科学系の専門家を主体に多彩な顔ぶれになっております。ご期待下さい。先着順定員70名で4月30日まで受講募集を行っています。[村上]
| 第1回 | 5月10日(月) | シベリアの森林は壊れているか 高橋邦秀(北大農学部) |
| 第2回 | 5月13日(木) | 21世紀の北極海航路 北川弘光(北大大学院工学研究科) |
| 第3回 | 5月17日(月) | 流氷の世界 青田昌秋(北大低温科学研究所) |
| 第4回 | 5月20日(木) | ロシア極東地域の経済開発 杉本侃(日ロ経済委員会事務局長) |
| 第5回 | 5月24日(月) | 日ロの渡り鳥とその保護 藤巻祐蔵(帯広畜産大学畜産学部) |
| 第6回 | 5月27日(木) | 北の海の哺乳類と共存するには 和田一雄(野生生物保護学会会長) |
| 第7回 | 5月31日(月) | サハリン大陸棚石油・ガスの開発と環境 村上隆(センター) |
当センターは、定例の国際シンポジウムを7月21日(水)午後から23日(金)にかけて開催いたします。本年度は「ロシアの地域:経済成長と環境」と題して、ロシアの地域における持続的な経済発展と環境保全の問題に焦点を合わせ、自然科学の分野も取り込んだ学際的な内容になっております。
現段階で参加を予定している研究者の報告テーマは以下の通りです。[村上]
(1)基調講演
| ・P. ハンソン(英国、バーミンガム大学)「ロシアにおける経済変動の地域類型」 |
| ・V. ダニロフ・ダニリヤン(ロシア、国家環境委員会議長)「シベリア・極東の経済発展と環境保護:トレードオフの問題」 |
(2)パネル1「地域の次元から見たロシア金融危機」
| ・久保庭真彰(一橋大学)「ロシア先進地域における金融危機」 |
| ・P. ラトランド(米国、ウェズレイヤン大学)「ロシア経済発展の代替案における地域の問題」 |
(3)パネル2「ロシアの地域間資金循環」
| ・E. ガヴリレンコフ(ロシア、経済大学)「ロシアの地域特性と地域間の資本循環」 |
| ・荒井信雄(札幌国際大学)、A. ベロフ(福井県立大学)「サハリン州の財政」 |
| ・V. ルデンコ(ロシア、科学アカデミー・ウラル支部哲学・法研究所)「ウラル地域の近代化の要請に対する経済的・法的対応」 |
(4)パネル3「ロシアの地域労働市場」
| ・V. ギンペリソン(ロシア、IMEMO)「ロシアの地域における公務員雇用と再分配政策」 |
| ・大津定美(神戸大学)「移行期ロシアにおける地域労働市場の発展類型」 |
(5)パネル4「海洋汚染」
| ・R. ステイナー(米国、アラスカ大学)「アラスカにおける海洋汚染の経験とオホーツク海」 |
| ・A. レオーノフ(ロシア、科学アカデミー海洋学研究所)「サハリン大陸棚石油・ガス開発によるオホーツク海エコシステムの変化」 |
(6)パネル5「環境問題とNGO」
| ・A. ヴァシリエヴァ(米国、モントレー大学)「開発と環境に関するサハリンの市民意識」 |
(7)パネル6「海洋開発」
| ・北川弘光(北海道大学)「バレンツ海石油・ガス開発に伴う地域経済発展」 |
(8)パネル7「経済開発と先住民族」
| ・A. ナチョトキナ(サハリン州議会)「演題未定」 |
| ・E. ウィルソン(英国、ケンブリッジ大学)「演題未定」 |
(9)パネル8「中央アジアの環境問題と農業:アラル海を中心に」
| ・石田紀朗(京都大学)「演題未定」 |
| ・野村政修(九州国際大学)「イリ川下流域における水利用と利用料徴収の可能性:ベレケ村の場合」 |
3月31日をもって2000年度の外国人研究員の公募が締め切られました。現在、審査に向けて書類を整理中ですが、暫定的な数字では、応募件数は48件で、ほぼ昨年並みでした。国別(国籍ベース)・地域別に見ると、ロシア14件、ウクライナ7件をはじめとして、旧ソ連圏から26件、ポーランド4件をはじめとして、旧東欧圏から14件、これら以外の欧米圏から5件、アジアから3件となっています。4件以上の応募があったのは上に挙げた3カ国だけで、全部で17カ国の方々からの応募がありました。分野別では、歴史(考古学を含む)15件、政治(法律学、国際関係論、社会学を含む)12件、経済11件、文学・文化が10件となっています。これから審査が行われ、7月までに候補者3名が決定されます。
なお、1999年度の長期外国人研究員、シンシア・ウィタカー(ニューヨーク市立大学歴史学部)、リュー・クイリ[劉魁立](中国社会科学院少数民族文学研究所)、エカテリナ・ニコヴァ(ブルガリア科学アカデミー・バルカン問題研究所)の3氏は、6月1日から2000年3月31日までの10カ月間の滞在予定で、受け入れ準備が進められています。[田畑]
1999年度のCOE[Center of Excellence]外国人研究員として、以下の3氏がセンターに滞在することになり、受け入れ準備が進められています。
イサベル・ティラド(ウィリアム・パターソン大学歴史学部/米国ニュージャージー州) 研究テーマ:ネップ末期の農村コムソモール 滞在期間:6月25日〜12月25日
イーゴリ・クルプニク(スミソニアン研究所国立自然史博物館/米国ワシントンDC) 研究テーマ:シベリア少数民族聞き取り調査の分析 滞在期間:8月1日〜11月10日
ジェフリー・ハーン(ヴィラノヴァ大学政治学部/米国ペンシルヴァニア州) 研究テーマ:ロシア極東地域における民主主義の展望 滞在期間:12月21日〜2000年3月31日
3氏ともに米国からの招聘ですが、クルプニク氏はロシア国籍です。今年度滞在する方々からは、公募による選抜を行いました。昨年9月30日に締め切られた公募には、47名の応募がありました。センターでは、応募書類の審査に基づいて、12月3日の協議員会で3名の候補者を選び、文部省に申請しました。この3月に、文部省からの通知により、上記3名が正式に今年度のCOE外国人研究員として認められたわけです。これらの方々との研究交流をご希望の方はセンターまでご連絡下さい。
1月25日
| 報告者:村上隆(センター)「ロシアの石油・天然ガス産業への外国投資」 |
| 討論者:吉田文和(北大経済) |
3月4日
| 報告者:林忠之(センター)「チェコ政治の最近の展開−1998年選挙と社民党政権」 |
| 討論者:田口晃(北大法学) |
3月5日
| 報告者:山村理人(センター)「ロシアの食糧事情:畜産物の需要と輸入の分析」 |
| 討論者:野辺公一(農水省農業総合研究所) |
3月12日
| 報告者:上田理恵子(センター)「アウスグライヒ体制下のハンガリー陪審法制」 |
| 討論者:家田修(センター) |
3月12日
| 報告者:デーヴィッド・ゴールドバーグ(文部省研究留学生)“An Examination of American Intervention in the Kurile Islands: Dispute During the Cold War Era” |
| 討論者:皆川修吾(センター) |
年度末に集中するきらいがありましたが、とにかくこの期間に上記5つの研究員セミナーが開催されました。今年度中に開催された12回の研究員セミナーでも参加者全員が各自コメントするという伝統が厳守されました。この慣行は学際的な視点からコメントするため研究当事者にとって厳しくも有意義なアドバイスとなることが多く、同時に参加者である専任研究員それぞれに事前に配布されたペーパーを、たとえ専門分野が異なっていてもかなりの程度理解する努力が要求されます。このような適度な緊張感と論証プロセスを経て、より精緻された論旨がペーパーに生かされることになります。専任研究員セミナーで報告されたペーパーの多くが今年度も学術的批判に耐えうるペーパーとして学術書や紀要に掲載されることを願っています。[皆川]
私は本年2月1日よりインターネットのホームページ『日露歴史情報センター』を開設致しました。今までロシアの友人を通じ、色々の資料を入手してきましたが、これを手元に私有しているより、資料の必要な方にお渡し致し多少でもお役に立て度いと考えています。又、今後の資料入手に利用願ったら幸いと存じます。現在所有しているものについては下記URLにアクセスいただければお分かり願えるかと存じます。主としてノモンハン事件、満州侵略、日本軍抑留等のビデオカセットや写真類ですが、他に日本におけるロシア人軍人の墓地の資料等も所有しております。
因みに、本年はノモンハン事件の60周年に当たり日本軍人捕虜にて残留された方々を日本に招待したいと考えており、若し情報をお持ちの方はご教示を得たいと考えています。
| 鈴川正久 |
| 〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町4-155-2 |
| TEL/FAX:06-6491-9033 e-mail:russia-j@interlink.or.jp |
| 日露歴史情報センターURL:http://home.interlink.or.jp/~russia-j |
ニュース76号以降の北海道スラブ研究会とセンター特別研究会の活動は以下の通りです。[皆川]
| 2月1日 | Z. シュチャストニー(スロヴァキア科学アカデミー・社会学研究所)“The Main Directions in the Transformation of Economy and Agriculture in Slovakia” |
| 3月15日 | “Перспективы реконструкции в Таджикистане : Встреча с представитеями Комиссии по националъному примирению(КНП)” |
| 3月15日 | 「ハンティの熊祭り Bear Fest of the Khanty」1.VIDEO記録上映 解説:谷本一之(道立アイヌ民族文化研究センター所長)2.「北ハンティの熊祭りについて」 タチヤナ・モルダノヴァ(オビ・ウゴル復興学術研究センター副所長)、チモフェイ・モルダノフ(オビ・ウゴル復興学術研究センター・フォークロア部門リーダー)(北海道スラブ研究会) |
| 3月16日 | A. ニャージー(ロシア科学アカデミー・東洋学研究所)“Проблемы демократизации и охраны окружающей среды в Центральной Азии” |
| 3月18日 | 平成11-13年度科学研究費補助金国際学術研究「脱共産主義諸国におけるリージョン及びサブリージョン政治」プレ企画・研究会 1)「ポーランドの地方制度−1998年の改革を中心に」仙石学(西南学院大学)2)「ウクライナの第三の道? トランスカルパチヤ州の政治」松里公孝(センター) |
| 3月24日 | 寺尾信昭(大阪外国語大学)「アウスグライヒと共生:マジャール=ユダヤ同盟」 |
| 3月25日 | 「EU拡大と東欧−農業問題をめぐって−」(1999年度国際学術研究「旧ソ連東欧地域における農村経済構造の変容」準備研究会)1)「EUの農政改革と東欧」 柘植徳雄(東北大学)2)「東中欧政治における農業問題」 林忠行(センター) |
| 3月29日 | 松井憲明(釧路公立大学)「アルタイ地方の農村−1956年」(北海道スラブ研究会) |
| 4月23日 | ピョートル・クラフチェンコ(駐日ベラルーシ共和国大使)「ベラルーシ共和国の過去・現在・未来」(北海道スラブ研究会) |
| 4月27日 | I. ベネット(ハンガリー科学アカデミー・経済学研究所)“The EU Enlargement: Finnish Experiences and Hungarian Dilemmas” |
| 4月28日 | B. ダラーゴ(トレント大学/イタリア)“Asset Specificity, Stability and Change of the Economic System: Transition in Central-Eastern Europe” |
2月17日の全学評議会で北大附属図書館長の選考がおこなわれました。候補者は、文系4学部長および工学部長の推薦を受けたセンターの原暉之教授のみで、投票の結果、同教授が選出されました。原教授は1997年に図書館長の重責に就かれて以降、数々の新機軸を打ち出して図書館の発展に尽力されました。その実績が高く評価されて再任の運びとなり、4月1日に就任されました。[井上]
本年度は当初から3名の非常勤研究員枠が認められました。したがって、公募により1998年4月に採用された2名および9月採用の1名、都合3名の全員を、規程および各自の希望に基づき、本年度もCOE非常勤研究員に引き続いて採用することが可能となりました。
上田理恵子(うえだ・りえこ)
一橋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学 オーストリア・ハンガリー法制史専攻
金 成浩(きむ・そんほ)
東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程単位取得退学 ロシア外交史専攻
久保久子(くぼ・ひさこ)
北海道大学大学院文学研究科博士後期課程修了 ロシア文学専攻
上記3名の方々には、これまでと同様、センターの共同研究にかかわる補助業務を担当するなかで、それぞれの研究を進めていただくことになります。
1999年度は、次の方々に客員教授をお願いすることになりました。[井上]
阪本秀明氏(天理大学・国際文化学部)
今年度の比較経済体制学会の全国大会は、6月3日(木)〜5日(土)に横浜国立大学で開催される。プログラムは以下のとおり。[田畑]
| 6月3日(木) | ||
| 13:00〜16:00 数量経済研究会 | ||
|
|
||
| 6月4日(金) | ||
| 10:00〜12:30 自由論題 | ||
|
|
||
| 14:40〜17:40 共通論題(1) | ||
|
|
||
| 6月5日(土) | ||
| 10:00〜12:00 共通論題(2):招待講演 | ||
|
|
||
| 13:00〜17:00 共通論題(3):討論 | ||
|
| 5月29日 | 日本ロシア・東欧研究連絡協議会(JCREES)発足記念シンポジウム「日本におけるロシア東欧研究の現状と国際交流の課題」 於上智大学 第1部「日本におけるロシア東欧研究の現状と展望」、第2部パネルディスカッション「国際交流の諸問題」 連絡・照会先:上智大学外国語学部 宇多文雄 fax: 0466-43-7730 Email: f-uda@hoffman.cc.sophia.ac.jp電話(月、水、金10:00〜16:00)03-3238-3907 上智大学ロシア語研究室 登坂礼子 |
| 6月4〜 5日 | 比較経済体制学会第39回大会 於横浜国立大学 共通論題は「国際経済・国際金融と移行経済」 前日の6月3日に数量経済研究会開催 |
| 6月後半(未詳) | ロシア科学アカデミー極東支部極東諸民族歴史・考古・民俗学研究所他主催「21世紀の歴史教育における東アジア史:教育者と研究者の対話」 於ウラジオストク市(未詳) 連絡・照会先:上記研究所所長 V. L. Larin教授 ロシア極東における東洋学教育100周年を記念して、東アジア史教育の現状と将来を論じる 97年10月に上越大学で行われた同趣旨の大会の継続 |
| 7月21〜23日 | スラブ研究センター1999年度夏期国際シンポジウム |
| 10月9〜10日 | ロシア史研究会大会 於明治大学リバティ・タワー |
| 11月18〜21日 | AAASS(米国スラブ研究促進学会)の第31回大会 於ミズーリ州セントルイス パネルの募集締切は1998年12月9日 |
| 2000年7月29日〜8月3日 | ICCEES(中・東欧研究世界学会)第6回大会 於タンペレ |