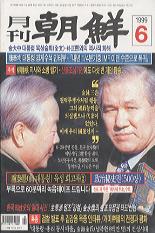 周知のごとく、盧泰愚は、1988年2月から93年2月まで韓国大統領職にあったものの、退職後の96年(金泳三政権時代)に収賄疑惑から一時囚われの身となった。その後、恩赦により釈放され、現在は隠遁生活を送っている。盧泰愚の大統領在位期間は、東アジアのバランス・オブ・パワーに大きな変動をもたらした出来事が集中した時期でもあった。そのため、韓国政治研究だけでなく国際関係史研究という観点からも、彼がどのような証言をするか興味深いとも言える。
周知のごとく、盧泰愚は、1988年2月から93年2月まで韓国大統領職にあったものの、退職後の96年(金泳三政権時代)に収賄疑惑から一時囚われの身となった。その後、恩赦により釈放され、現在は隠遁生活を送っている。盧泰愚の大統領在位期間は、東アジアのバランス・オブ・パワーに大きな変動をもたらした出来事が集中した時期でもあった。そのため、韓国政治研究だけでなく国際関係史研究という観点からも、彼がどのような証言をするか興味深いとも言える。
今年4月、現代韓露関係に関する資料を収集するためソウルにおこなった。世宗研究所や国会図書館などをまわり先行研究は集めることができたものの、まだ一次資料へのアクセスは望むべくもなかった。今回はここで手を打ってもう一度しきり直しと考えていた時のことであった。地下鉄の売店に、「月刊朝鮮」誌の広告が貼り出されていた。そこには、盧泰愚元大統領が16時間にも及ぶインタビューに答えたという大きな見出しが踊っていた。
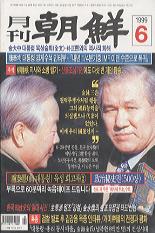 周知のごとく、盧泰愚は、1988年2月から93年2月まで韓国大統領職にあったものの、退職後の96年(金泳三政権時代)に収賄疑惑から一時囚われの身となった。その後、恩赦により釈放され、現在は隠遁生活を送っている。盧泰愚の大統領在位期間は、東アジアのバランス・オブ・パワーに大きな変動をもたらした出来事が集中した時期でもあった。そのため、韓国政治研究だけでなく国際関係史研究という観点からも、彼がどのような証言をするか興味深いとも言える。
周知のごとく、盧泰愚は、1988年2月から93年2月まで韓国大統領職にあったものの、退職後の96年(金泳三政権時代)に収賄疑惑から一時囚われの身となった。その後、恩赦により釈放され、現在は隠遁生活を送っている。盧泰愚の大統領在位期間は、東アジアのバランス・オブ・パワーに大きな変動をもたらした出来事が集中した時期でもあった。そのため、韓国政治研究だけでなく国際関係史研究という観点からも、彼がどのような証言をするか興味深いとも言える。
「盧泰愚証言」は、「月刊朝鮮」誌(ソウル、朝鮮日報社)五月号から連載され始めた。「月刊朝鮮」誌記者とのインタビューは総計16時間にもおよび、5月号はおもに外交に関する彼の証言が掲載された。盧泰愚は、自身の進めた北方政策、すなわち韓ソ国交回復(1990)、韓中国交回復(1992)等について、韓国側の舞台裏を交えて回想している。また、6月号では主に内政についても語り、韓国内でも大きな関心を集めた。6月号には盧泰愚自身の肉声テープ(60分)も雑誌の付録としてつけられた程であった。彼の回想は5月号と6月号合わせて総計約150ページにものぼり、さらに7月号にも続く予定である。この証言は、日本でも「読売新聞」(99年4月22日付朝刊)に紹介された。「読売新聞」は主に朝鮮半島南北関係に関連する部分を取り上げ、北朝鮮の故金日成主席が92年に特使を派遣し盧大統領を北朝鮮に招待していたという証言に注目し報道している。だが、盧泰愚はこの他、韓ソ関係についても面白いエピソードを述べている。以下、そのいくつかを拾い上げてみた。
盧泰愚時代に進められた韓国の北方外交について、彼自身は「遠交近攻」という言葉で説明している。この「遠交近攻」というのは、中国戦国時代の魏の范雎が秦の昭襄王に献じた外交政策に由来し、遠国と親しく交際しながら近国を攻略するという戦略を指す言葉である。このあたりは、軍人出身大統領の発想を表してもいると言えるだろう。また、韓ソ国交回復が、一時韓国のマスコミから「金で買った」という非難を受けたことに対しては、彼の進めた北方外交の成果を強調するトーンで反論している。韓国は、国交回復に際し、30億ドルの経済援助をソ連に与えることになったが、この30億ドルという金額が、当時の韓国にとって決して安くない額であったことは言うまでもない。これに対して盧泰愚は、韓ソ国交回復後にソ連が北朝鮮に対し国際友好価格での石油供給をやめ、それによって北朝鮮が多大な経済的打撃を受けたこと、ソ連から北朝鮮への戦闘機や武器供与が中断されたことなどの成果を強調し、30億ドルの借款は決して無駄ではなかったと反論した。
1990年9月30日の電撃的な韓ソ国交回復に遡ること約4ヶ月、6月初めに盧泰愚とゴルバチョフは米国サンフランシスコで初の首脳会談をおこなった。この会談の事前準備には、非公式ルートが使われたとし、盧泰愚は以下のように述懐した。
「サンフランシスコ頂上会談は、どちらが先に提議したかはっきりとしない。お互いの間にサインが行き交った時だったからだ。1990年5月にゴルバチョフソ連大統領が自分の外交顧問であるドブルイニン(前駐米大使)を私に送った。韓国で開催されていた元国家首脳会議(IAC:Inter Action Council)参席を理由に訪韓したドブルイニンは、私にソ連との経済協力に対する意志を打診し、『ソ連は修交の意志を持っているが、韓国で会うことはできないので、ワシントンでの米ソ会談前後にサンフランシスコで会う用意がある』というゴルバチョフの意志を伝達した」
ゴルバチョフが韓国で会わなかったのは、北朝鮮との関係を意識したからだと見られるが、盧泰愚は、「ゴルバチョフのドブルイニン特使の派遣は、韓ソ国交樹立に慎重であったソ連外務省や軍部を意識してのことでもあった」という見解も示している。また、サンフランシスコ韓ソ頂上会談での具体的な会談内容についてまでは言及はしていないものの、この会談でのゴルバチョフとの面白いやり取りを披露した。
「1990年6月5日、私がサンフランシスコでゴルバチョフと最初に会った時、彼は『今凍った氷が溶け始めている。私たちの会談事体が解氷である』と言った。私はこの言葉を受けて、修交を念頭において『すでに私たちは果実を収穫する時期が来たようですね』と述べた。そしたら、ゴルバチョフは『果実は熟して食べないと。熟する前に食べれば、お腹をこわすでしょう』と言ったので、私は『一回試して見てください。東洋の盧某は我慢して待つことには誰にも引けをとりません。これだけ我慢して待っている盧某が『今、包んで食べましょう』と言った時は、すでに食べごろなのですよ』と言ったら、雰囲気が自然に出来上がっていたのを記憶している」
この後、90年9月30日に国連ニューヨーク本部で、ソ連のシェワルナゼ外相と韓国の崔浩中外相との会談がおこなわれ、両国の国交締結が合意された。修交後、盧泰愚は90年12月に、モスクワを訪問している。翌91年4月、ゴルバチョフの日本訪問後、韓国南部沖にある済州島で三度目の韓ソ頂上会談がおこなわれた。ゴルバチョフの離日後、当時の日本のマスコミは日ソ首脳会談の評価に忙しく、ゴルバチョフがモスクワへの帰途に立ち寄った済州島での会談に関しては、詳しく報道できていなかったように思える。ゴルバチョフは、この済州島会談で、韓国の国連加盟に対してソ連は拒否権を発動しないという約束をおこなった。離日直後のゴルバチョフの様子について、盧泰愚はこう述べた。
「ゴルビーとの済州島頂上会談時には、もう両国が修交した上であったし、回数も3回目の会談になるため、かなり親しい状態にあった。ゴルビーは当時、日本訪問中に北方領土問題をはじめとする日ソ間の懸案問題が思った通り行かず、力がない状態だった。彼は大変気分が良くないように見えた。私は、彼をかわいそうに思い、この二人(ゴルバチョフとライサ)を慰労しようと頑張った。そして、オープンしたばかりの済州新羅ホテルの部屋をおさえて、この二人に『日本での事は忘れてください。まあ、新婚旅行に来たと考えて下さい。私があなたたち新婚夫婦のために部屋を一つ取っておきましたから、全てを忘れて今日の私との夕食まで二人はゆっくり休んでください。私が今すぐ慰労できることはこれぐらいしかありませんが?』と言った。そしたら、二人は感銘を受けたような様子であった。ゴルバチョフの夫人であるライサ女史は、その時ソ連の国内世論を意識しているようだった。済州島の海女達と水産物を売るところを回って見ながら、ただ見物するだけでなく、魚を触って写真を撮りテレビに出るようにした」
この時期、ソ連側にとって、経済協力という要因から対日外交と対韓外交は密接に連繋していたのであろう。皮肉なことに日ソ関係が北方領土問題で進展しないことが追い風となって、その間に韓国とソ連の関係は緊密化していったようである。
*
その他、盧泰愚の回想の中には、ゴルバチョフが利子の概念をまったく理解していなかったように見えたというエピソード等も盛り込まれている。また、北方政策全般に関して語る中で、盧泰愚は自分の後任となった金泳三前大統領が、北朝鮮との関係を冷却させてしまったことに対し、「これほど苦労して手綱を引っ張ってきたのに?」という複雑な心情を吐露した。さらに、6月号では「金泳三民自党代表の国政運営能力を疑ったが、他に代案がなく後継者にするようになった。?彼(金泳三)は民主主義とは関係のない、権力を勝ち取るためにすべてのことをやり尽くした人間だった。だから、私は色盲患者であった」として、金泳三を後継に指名した自分の眼力を悔いてもいる。
全体的に、盧泰愚自身の大統領時代の実績をアピールする形で証言が進んでいることは否めない。本人の回想である以上これは避け難いのだろうが、そこから資料的価値を引き出すのは研究者の腕の見せ所といったところになるだろうか。少なくとも、彼の証言は韓国政治外交研究、韓ソ関係研究ばかりか東アジア国際関係研究にも一つの資料を提示したのは間違いないだろう。インタビューだけに留まるのではなく、さらに、彼自身の手による本格的回想録の執筆が待たれる。