
|
山村理人研究員の著作『ロシアの土地改革:1989〜1996年』(多賀出版、1997年)が1998年度日本農業経済学会学術賞を受賞しました。この賞は、毎年同学会の会員1名に対して与えられる同学会の賞のなかでもっとも権威のあるもので、4月2日に千葉大学で表彰式がおこなわれました。[編集部] |
1998年7月22日(水)
◆ 1998年度夏期国際シンポジウムの開催 ◆
本年度の夏期国際シンポジウムは、「地域」をキー概念として、人文社会科学を横断するものとして開催されます。上記のプログラムに示されるように、北米、西欧、東欧、ロシア、ウクライナ、中央アジアの第一線の研究者がここに結集します。 1989年以降のスラブ世界の変動は、スラブ学における地域実証研究の地位を不動のものとしたといえましょう。一方では、主権国家の枠組みを通じてこのエリアを見るのでは不十分だということが示され、他方では、地方の古文書・現地調査などに立脚した研究が現に可能になったからです。過去数年間、人文社会科学の諸領域においてスラブ圏の地域を対象とした調査が蓄積され、研究の現状は、個別事例研究から地域間比較、一般理論構築への飛躍が求められている段階だと言えましょう。 スラブ「地域学」は学際性を必要としています。たとえば、地域の歴史的アイデンティティーと住民の投票行動の間の相関関係などは、東欧でもロシアでもウクライナでも注目されているのに、従来、分野別の学会しか開催されず、歴史学者と政治学者の間の対話の場がなかったため、こうした問題を検討する場がありませんでした。旧ソ連や北米における過度に専門分化したスラブ学の現状に鑑みても、北大スラブ研究センター以外にこうした学際的シンポジウムを開催しうる機関が世界に存在するとは考えられません。本シンポジウムは、スラブ「地域学」の世界的な飛躍の場となるでしょう。[松里] ◆ 「移行期の中央アジア」セミナーの開催 ◆ センター夏期国際シンポジウムに先行して7月22日(水)13:00〜15:30に、現在日本滞在中の中央アジアの研究者を招いて「移行期の中央アジア」というテーマでセミナーをおこないます。会場はセンター内です。皆様の参加をお待ちします。[宇山] A. ショマノフ(カザフスタン発展研究所)「カザフスタンにおけるロビイズムと圧力団体:歴史と現在」(ロシア語)|
|
|
|
|
|
| 森永 貴子 |
一橋大・院 博士課程 |
98.7.22〜7.31 | 原 暉之 | イルクーツク及びシベリア諸都市(特にトムスク)の市会活動における商人の役割 |
| 河本 和子 |
東大・院 博士課程 |
98.7.21〜8.3 | 皆川修吾 | 社会集団としての法律家の政治的・社会的位置づけおよびソ連における法(実定・判例)の意味 |
| 上野 理恵 |
早大・院 博士課程 |
98.7.21〜8.4 | 村上 隆 | ヴルーベリの創作をめぐる言説について。シンボリストが作り上げたヴルーベリの神話の形成の考察 |
| 半谷 史郎 |
東大・院 博士課程 |
98.7.21〜8.7 | 宇山智彦 | 帝政時代のドイツ人およびヴォルガ・ドイツ人自治共和国に関する資料収集 |
| 畠山 禎 |
名大・院 博士課程 |
98.7.21〜8.10 | 家田修 | 19世紀後半ロシアにおける建設労働者の日常生活:ペテルブルグを中心に |
| 光吉 淑江 |
アルバータ大 Ph.D.コース |
99.1.18〜2.1 | 松里公孝 | 第二次大戦後に強制移住れた極東のウクライナ人について |
| 村上隆 | 「サハリン大陸棚石油・天然ガスの〈開発と環境〉に関する学際的研究」 |
| 田畑伸一郎 | 「ロシアの地域間の資金循環」 |
| 村上隆 | 「サハリン大陸棚石油・天然ガス開発にともなう〈開発と環境〉に関する学際的研究」 |
| 望月哲男 | 「90年代ロシアにおけるポストモダニズム文芸の総合的研究」 |
| 田畑伸一郎 | 「ロシアの地域間資金循環の分析」 |
| 松里公孝 | 「ロシア連邦ヴォルガ中流域6民族共和国エリートの比較研究(バシコルトスタン、マリ・エル、モルドワ、タタルスタン、ウドムルチヤ、チュワシ)」 |
| 世話役代表: | 井上紘一(センター) | 世話役: | 大西郁夫(北大文)、匹田豪(小樽商大)、田口晃(北大法)、高岡健次郎(札幌学院大)、所伸一(北大教育)、徳永彰作(札幌大)、杉浦秀一(北大言語文化)、吉野悦雄(北大経済) | 会計係: | 松田潤(札幌大) | 会計監査: | 吉田文和 | (北大経済)連絡係: | 皆川修吾(センター) |
| 6月 3日 | V.E. セリヴョルストフ(ロシア科学アカデミーシベリア支部経済・産業工学研究所)「ロシアの新連邦制・地域政策下におけるシベリアの発展」(特別研究会) |
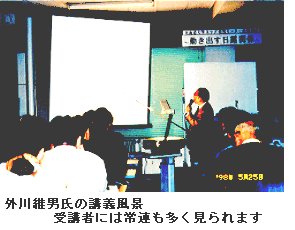 ペレストロイカ初期の1986年から毎年スラブ・ユーラシア地域の様々な問題をテーマとしておこなわれてきた本講座ですが、13年目にあたる今年は、新しい局面を迎えた日露関係をテーマとして取りあげました。昨年11月と今年4月の日露首脳会談を契機として、両国は国境の確定と共栄をテーマとした新しい関係の樹立に向けて動き出しています。今回の講座ではこうした動きを踏まえながら、両国関係の歴史・現状・将来をできるだけ広い視点から概観できるようなプログラムを組んでみました。
ペレストロイカ初期の1986年から毎年スラブ・ユーラシア地域の様々な問題をテーマとしておこなわれてきた本講座ですが、13年目にあたる今年は、新しい局面を迎えた日露関係をテーマとして取りあげました。昨年11月と今年4月の日露首脳会談を契機として、両国は国境の確定と共栄をテーマとした新しい関係の樹立に向けて動き出しています。今回の講座ではこうした動きを踏まえながら、両国関係の歴史・現状・将来をできるだけ広い視点から概観できるようなプログラムを組んでみました。
| 日 時: | 1998年7月21(火)夕〜7月24日(金)[3泊4日] |
| 場 所: | 藤屋旅館(〒389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻258-5)Tel.: 0262-58-2514 JR信越本線黒姫駅よりバスで野尻湖(終点)下車湖畔に向かって徒歩1分 |
| 費 用: | 参加費3,000円 1泊(3食付税込み)7,500円 |
| プログラム: | (発表順の変更が若干ありえる) |
| 日程: | 1998年10月30日(金) 夕刻集合、懇親会 10月31日(土) 午前・午後の各1セッションと総合討論 |
| 会場: | 北海道大学スラブ研究センター |
| 1998年7月21〜24日 | 第35回野尻湖クリルタイ(日本アルタイ学会)(記事参照) |
| 7月22日 | スラブ研究センターセミナー「移行期の中央アジア」(記事参照) |
| 7月22〜25日 | スラブ研究センター夏期国際シンポジウム「地域:スラブ・ユーラシア世界を映す鏡」(記事参照) |
| 7月23日〜8月2日 | 国際ドストエフスキーシンポジウム1998。於コロンビア大学、ニューヨーク 連絡・照会先:Robert L. Belknap, Slavic Dept. 708 Hamilton Hall, Columbia Univ. New York, NY 10027 USA. Tel. 212-854-3941; Fax. 212-854-5009; E-mail: dm387@columbia.edu |
| 9月10〜12日 | European Association for Comparative Economic Studies第5回コンファレンス“Economies in Transition and the Varieties of Capitalism: Features, Changes, Convergence”於バルナ、ブルガリア ペーパー募集中(締め切りは3月1日)連絡・照会先:Prof. Mitko Dimitrov, Institute of Economics, BAS, 3, Aksakov St. BG-1040 Sofia Bulgaria. Fax. 359-288-2108. |
| 9月24〜27日 | AAASS(米国スラブ研究促進学会)第30回年次大会 於フロリダ |
| 10月23〜24日 | 日本ロシア文学会1998年度総会・研究発表会(記事参照) |
| 10月24〜25日 | ロシア史研究会1998年度大会 於大阪大学 照会先:成蹊大学法学部 富田武(Tel.: 0422-37-3633; E-mail: tomita@law.seikei.ac.jp |
| 10月30〜31日 | 中央アジアセミナー(記事参照) |
| 2000年7月29日〜 8月3日 |
ICCEES(中・東欧研究世界学会)第6回大会(於タンペレ)(記事参照) |
スラブ研究センター和文紀要『スラヴ研究』は次号(第46号)の執筆申込みが締め切られました。原稿の締め切りは8月末、来年3月発行の予定で編集作業が進められます。
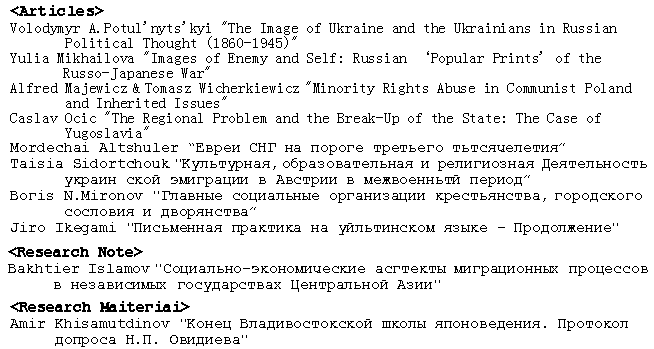

|
山村理人研究員の著作『ロシアの土地改革:1989〜1996年』(多賀出版、1997年)が1998年度日本農業経済学会学術賞を受賞しました。この賞は、毎年同学会の会員1名に対して与えられる同学会の賞のなかでもっとも権威のあるもので、4月2日に千葉大学で表彰式がおこなわれました。[編集部] |
| 5月 11日 | 木村汎氏(国際日本文化研究センター) |
| 5月 21日 | 和田あき子氏 |
| 5月 25日 | 外川継男氏(上智大) |
| 5月 29日 | M.L.レムニョヴァ(Remneva)氏(モスクワ大/ロシア)、N.A.ソロヴィヨヴァ(Solovieva)氏(同) |
| 6月 3日 | V.E. セリヴョルストフ(Seliverstov)氏(ロシア科学アカデミーシベリア支部経済・産業工学研究所) |