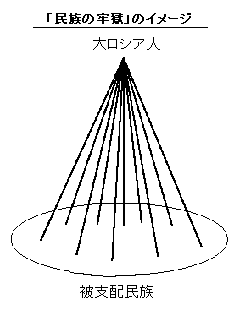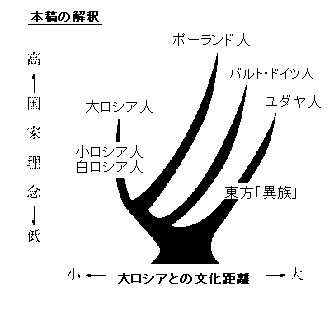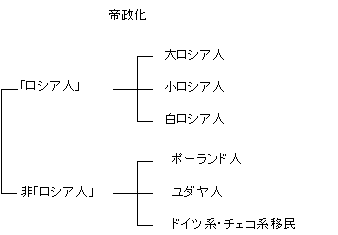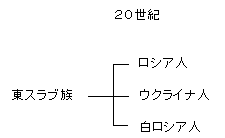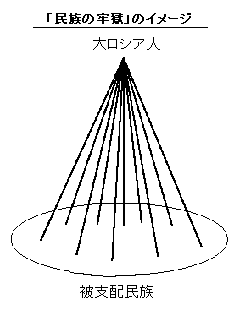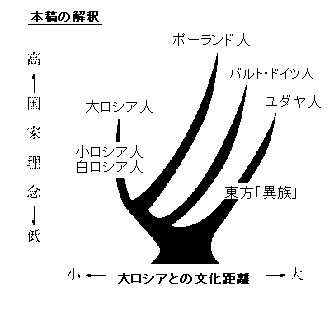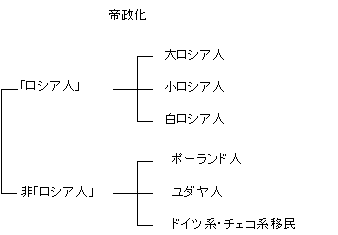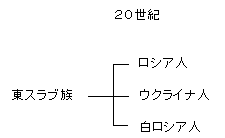19世紀から20世紀初頭にかけての
右岸ウクライナにおけるポーランド・ファクター
松 里 公 孝
Copyright (c) 1998 by the Slavic Research Center. All rights reserved.
「我々はかくも弱く、かくも無能だ。我々は、中央権力も西部地方における自分自身の力もあてにできないでいる。我々がどんなにポーランド人を恐れているか、まんいち彼らが知ったら!」(ロシア帝国内務大臣P.A.ヴァルーエフの日記:1865年4月6日)(1)。
はじめに
前世紀から今世紀にかけての右岸ウクライナ(2) ほど、その民族学的な相貌を大きく変えた地域は、世界的にみても稀であろう。そのターニング・ポイントは1917年革命であった。この革命は、第一に、レーチ・ポスポリータ(3) 分割後もこの地の支配階級の地位を譲ることのなかったポーランド系(4) 地主貴族を絶滅した。1920年代の土着化政策がウクライナ共和国に残住するポーランド人に一定の自己表現の機会を与えたのは事実であるが、趨勢としては、革命によって自らのエリートを失ったポーランド系住民は、今世紀を通じてウクライナ人に同化せざるをえなかった。第二に、この革命は、ツァーリ政府がユダヤ人に課していた居住制限(cherta osedlosti)を廃し、世界でも有数のユダヤ人密集地帯(したがって、反ユダヤ感情が強いことにかけても世界有数の地域)であった帝国西部諸県(5) からソ連中央部へのユダヤ人の漸次的移住を可能にした。この静かな大移動の結果がいかに顕著なものであるかは、こんにち、(ロシア政治とは対照的に)ウクライナ政治において「ユダヤ人ファクター」がほとんど存在していないという事実にも示されている。第三に、レーニンの民族自決原理に基づいて、ウクライナ・ソヴェト社会主義共和国が形成され、すくなくとも公式には、ウクライナ人がこの地を代表する民族として宣言された。
こうして、ルブリン合同(1569)以来初めて、東スラブ族が右岸ウクライナの実質的な(政治的のみならず社会・経済・文化的な)支配エトノスとなったのである。皮肉なことだが、東スラブ族がポーランド人とユダヤ人の優勢を打破した結果として、東スラブ族内部の対立、つまり、大ロシア人とウクライナ人の間の対立が前面に出ることになった。この過程を完成したのは、第二次世界大戦に前後してのプリカルパート・ウクライナ(ハリチナ)の併合と、そこで1947年に実施されたポーランド系住民の人民民主主義ポーランドへの強制移住であった。スターリニズムの残酷な膨張政策のおかげでウクライナは国土を統一し、ポロニズム(6) を国土から最終的に一掃することができたのである。これによって、ペレヤスラフ条約(1654)に始まるウクライナ史のひとつのサイクルは完了し、ウクライナ人は大ロシア人との「同盟」をもはや必要としなくなった。
本稿の動機となっているのは、この「大ロシア人・対・ウクライナ人」という特殊20世紀的な民族関係理解の枠組みが19世紀以前のウクライナ史に遡及的に投影されることによって、前世紀における右岸ウクライナのエスニックな相貌の理解が妨げられてきたという事実である。たとえば、1897年人口調査時の右岸ウクライナの大ロシア語使用住民数の対県人口比がヴォルィニ県において3.5%、ポドリヤ県において3.3%、キエフ県において5.9%にすぎなかった事実(7) は、読者を驚かすだろう。ポーランド分割後百年余を経て、大ロシア人はドニエプル川以西にはほとんど住んでいなかったのである。
ポーランド人が ム ナポレオンでさえモスクワまでしか到達できず、ヒットラーに至ってはモスクワまでも行けなかったのに ム 大ロシア人を打ちのめしてヴォルガ川にまで到達した唯一のヨーロッパ民族であることはよく知られているが、ポーランド分割後もロシア帝国西部諸県がポーランド系貴族の手中にあったことはあまり知られていない。19世紀前半の右岸ウクライナがポーランド語文学の大拠点であったこと、カトリック教会の膨張の最東端がカルパート山脈ではなくてドニエプル川であったことなどは、現代人にはイメージしにくいことであろう。他方、(ユダヤ人の小商人を主人公とする)ブロードウェイ・ミュージカルの古典『屋根の上のバイオリン弾き』の舞台が右岸ウクライナであることも知らない人が案外多いのではないだろうか。「ウクライナ問題」の所在そのものを認めなかった国権党、ロシア人民同盟などの帝政末期の大ロシア主義的右翼政党の活動家、また内戦期のデニキン軍の将校団の主なリクルート源が他ならぬウクライナ人自身であったという一見逆説的な事実(8) も、革命前右岸ウクライナにおけるポーランド人、ユダヤ人の優勢を無視しては理解されえまい。繰り返すが、ロシア革命以前の右岸ウクライナにおいては大ロシア人とウクライナ人のいずれもが劣弱なエトノス集団にすぎなかったのであって、両者の間の近親憎悪関係のみを研究しても、それは当時の右岸ウクライナの民族間関係の理解にはつながらない。
西側におけるウクライナ史研究は長くウクライナ・ディアスポラに独占されてきた。そのためもあってか、ウクライナ史におけるポーランド人やユダヤ人の運命が注目を集めることはなかった。社会主義時代のソ連史学は、いわゆる「解放戦争」時代、つまり左岸ウクライナのロシア帝国への併合時(17世紀)についてはポーランド・ファクターを当然ながら強調したが、どういうわけか近代の西部諸県におけるポーランド人地主とウクライナ人農奴・農民との関係を民族問題として捉えることを避け、それを純粋に階級的な矛盾として描いてきた(9)。帝政の崩壊に至るまで重要な意義を保ったポーランド・ファクターを強調することはソ連史学、つまり大ロシア主義史学にとって好都合だったはずなので、この史学史上の空白は奇妙であるが、おそらく、社会主義時代はソ連とポーランドが同盟国であったことを反映しているのではないだろうか。こうして、ウクライナ史におけるポーランド人の運命は、ポーランド人民共和国において細々と研究されるのみだったのである(10)。不幸にして、この状況は、1992年以降のディアスポラ史学の独立ウクライナへの逆輸入と公式史学化(単一のウクライナ民族主義史学の形成)によって強まった。こうして現出したのは、ウクライナ史がウクライナ民族史と混同され、ウクライナ民族史がウクライナ民族運動史と混同される(11) 状況であった。この二重の混同の結果、ウクライナ人の民族運動さえ研究すればウクライナ史が理解できるかのような誤解が生まれたのである(12)。
では、ウクライナ人だけではなく、ポーランド人やユダヤ人も視野に入れさえすれば帝政下右岸ウクライナのエスノポリティクスが十分に分析できるかというと、そうではない。現にウクライナでは、第二次ポーランド反乱から第一次世界大戦以前の時期について、ナヂヤ・シチェルバクによってそのようなカンヂダート候補論文が書かれ、1995年に学位が取得されている(13)。しかし、この論文は野心的である点で好感が持てるものの、「民族の牢獄」パラダイムに強く拘束されており、右岸ウクライナにおけるツァーリ政府の小ロシア人政策、ポーランド人政策、ユダヤ人政策をバラバラに扱っている。その結果、政府はウクライナ人を抑圧しました、ポーランド人も抑圧しました、ユダヤ人も抑圧しましたといった水準の結論しか出てこない(14)。一般に、民族間関係の理解なしに民族政策の分析ができるはずがない。これは、帝政期の右岸ウクライナについては特に言えることである。なぜなら、当時の右岸ウクライナのように支配エトノスが劣勢にあったところでは、政府はエトノス集団間の矛盾・反目に付け入ることによってしか支配を維持できなかったからである。
民族間関係の深い理解に立脚して南西3県あるいは西部諸県におけるロシア政府の民族政策を丁寧に分析した最近の研究として、ダニエル・ボヴォアの『貴族、農奴、検察官』(初版フランス語版は1985年出版)(15) と、ヴィトルド・ロドキエヴィチの学位論文(1996)(16) が挙げられる。本稿もこれらの労作と方向性を共有するものである。
誤解なきよう予め断わっておくが、本稿は、「民族の牢獄」パラダイムがツァーリ政府の民族政策を過度に残酷に描く傾向がある点を問題にしているのではない。そもそも、ツァーリ政府の民族政策がどの程度寛容だったか、あるいは不寛容だったかなどという議論には、あまり意味がない。伊東孝之の至言を借りれば、平和とは概して抑圧的なものである。大切なのは、民族政策を貫く論理を明らかにすることである。「民族の牢獄」パラダイムが有害なのは、それがこの作業を妨げるからである。
以下、次節で、ロシア帝国の民族政策一般の特徴を概括し、第2節では、その特徴が右岸ウクライナにおいてどのように現われたかを考察する。第3節で、人口、土地所有、選挙、宗派対立などに表現された右岸ウクライナにおける民族間の力関係を検討し、最後にまとめを行なう。
1. 帝国の構造と機能
ロシア帝国の民族政策に関する近年の西側の研究は、「民族の牢獄」なるロシア帝国イメージに対して次第に懐疑的になっている。管見では、この懐疑論には三つの方向がある。第一は、帝国は被支配民族内部の階級矛盾を利用すること、言い換えれば、異民族の支配階級を「ロシア化」して帝国支配階級に組み込むことによって膨張するという考え方であり、J.P.ルドンに代表される(17)。もっとも、被支配民族の支配階級を懐柔することは帝国主義・植民地主義と矛盾するものではないという主張は当然成り立つから、ルドンの説は「民族の牢獄」論への根底的な批判ではない。弱い懐疑論とでも呼ぶことができよう。
第二の方向は、「民族の牢獄」論が、帝国の構造を、単一の支配民族を頂点に戴き、複数の被支配民族を同一底面上に置く円錐状に理解するのに対し、ロシア帝国の基礎にあったコスモロジーをもっと実証的・構造的に分析しようとするものである。この立場の代表格はA.カペレル(Kappeler)であるが、残念ながら本稿の著者にはドイツ語の読解力がないので、1992年に発表された、彼の名高い代表著作の内容をここで紹介することはできない。最近露語で発表された彼の論文(18) においては、ロシア帝国の「エスニックな位階制」は、政治的忠誠心、身分制、ロシア人との文化距離という三つの基準から形成されていたとされる。政治的忠誠心について付言すれば、19世紀のポーランド人は、まさにこの基準から帝国位階制の階梯を転げ落ちた典型であった。身分制について付言すれば、かつてレーチ・ポスポリータの被支配階級を形成していた「フィン人、エストニア人、ラトヴィア人、リトアニア人、白ロシア人、ウクライナ人」は、まさに自前の地主エリートを有していなかったために、文章語をはじめとする民族文化を発展させることができず、また自分たちの「代表」を帝国支配階級に送り込むこともできずに、帝国位階制において非常に低い地位に甘んじざるをえなかったのである。
カペレルの説を参考にしながら、ロシア帝国のコスモロジーについての著者なりの観察を述べれば、それは、大ロシア人との文化距離を横軸とし、政治文化の水準(あるいは、国家性の発達の度合い)を縦軸とする樹形をしていた(〈図1〉参照)。横軸は、「東スラブ族 ム それ以外のスラブ族 ム スラブ族以外のキリスト教徒 ム 非キリスト教徒」という形で表わされ、縦軸は、「非歴史的民族 ム 歴史的民族にして大ロシア人よりも国家理念の発達水準が低いもの ム 歴史的民族にして大ロシア人よりも国家理念の発達水準が高いもの」という形で表わされた。
〈図1〉ロシア帝国のコスモロジー
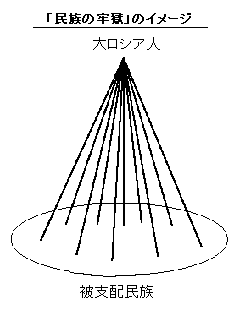
|
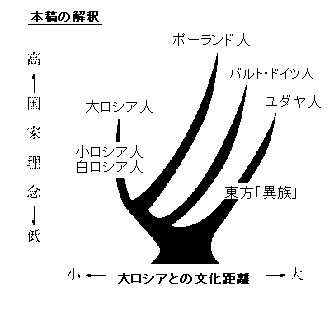
|
ロシア帝国のコスモロジーがハプスブルク帝国などのそれと比べて際だっているのは、帝国の西への膨張の結果、支配民族である大ロシア人よりも文化水準の高いエトノスを帝国領に抱え込んでしまったことをあっさりと認めてしまうことである。ただし、この認識が膨張への慎重論に転化するわけでは必ずしもなく、むしろ、「我々大ロシア人の文化は未熟・粗野であるが、それだけに若く力強い。この若さ、力強さゆえに、我々は西に向けて膨張する権利があり、また帝国内における西・中欧文明の代表者たる沿バルト貴族やポーランド貴族を支配する正当性を有している」とでも要約すべき膨張論に転化することがしばしばであった(19)。
カペレル説、松里説のいずれをとるにせよ、ロシア帝国のコスモロジーが上述のような樹形をとっていたとすれば、「民族の牢獄」論は、それを分析するのに適切な道具にはならない。なぜなら、ロシアの国家性への最も恐るべき(したがって敬われるべき)敵とされたポーランド人に対する政策と、独立したエトノスであるとさえみなされなかったウクライナ人に対する政策とを同一の範疇にくくることはできないからである。そもそも、「民族の牢獄」論、つまり円錐状の帝国構造認識は、1905年革命に前後して、被支配民族の統一戦線を形成しようとする民族運動指導者の実践的な関心を動機として広汎に普及したように思われる(言い換えれば、円錐状の帝国構造認識は、被支配民族の統一戦線を形成する上で都合がよかった)。つまり、その生まれからして、この議論は、帝国の構造と機能を内在的に理解するためのものではなかったのである。
「民族の牢獄」論を克服する第三の方向は、他民族の文化的同化という意味での「ロシア化」は、当時の行政手段の発達の度合いからいって、そもそも不可能であったとするものである。この立場を代表するレイモンド・ピアソンは、「民族の牢獄」パラダイムを、ツァーリ帝国に対する「ユダヤ人亡命者的な見解」であるとして退けた。彼によれば、統治能力の限界、官僚制と中央集権の未発達ゆえに「民族的少数派を同化しようとするような全体主義的野心も近代的な資源も有していなかった」ツァーリ政府が追求した「ロシア化」とは、「ロシア語、ロシア文化、ロシア的制度のヘゲモニーを強化すること」以上のものではなかったのである(20)。
本稿の課題との関係で特に重要なのは、この第三の立場である。そもそも帝国とは(国民国家とは対照的に)マスコミ・公教育・官僚制などの統治のテクノロジーが発達していなかった歴史段階における国家編成の方法であった。こんにちのウクライナ政府が行なっているように、朝から晩までテレビを動員して民族主義的な宣伝をするようなことは、ツァーリ政府には望むべくもなかった。また、ウクライナ政府は、独立後5年間のうちに、理系・医学系の一部の高等教育を除くほとんどの教育機関からロシア語を追放したが、そもそも義務教育の導入からさえ遠いところにあったツァーリ体制にこのような偉業は望むべくもない(学校の普及が遅れていた帝国南西地方においては特にそうであった)。このような低い統治テクノロジーの下で、しかも当時の西部諸県のように東スラブ族が社会経済的に劣勢にあるところで政治権力を維持することはいかにして可能か。それは、各エトノス集団の内部自治と自己表現 (osoblivost') をある程度まで容認し、それによって生まれるエトノス集団間の矛盾・反目を利用しながら、それらと取り引きすることによってのみ可能となるのである。つまり、ウクライナ人農民に対しては、「ポーランド人、ユダヤ人の搾取からあなたたちを解放してあげよう。我々大ロシア人と共にポーランド人・ユダヤ人の土地所有と闘おう」 と呼びかけ、他方、ポーランド人貴族やユダヤ人に対しては 「農民運動(あるいはポグロム)からあなたたちを護ってあげよう」と甘言を供する。こうして全てのエトノス集団に恩を売り、それらの忠誠をかちとるという、いわばエスニック・ボナパルティズムを展開しなければならないのである。この点では、ツァーリ政府は、「分割し、統治せよ」という世界史古代以来の帝国支配の根本原則に忠実だったのである。もちろん、「分割・統治」が成功する前提は、エトノス集団の自己表現・相互反目が統御可能な枠内にとどめられ、また大ロシア人のヘゲモニーが一定の水準にあることである。これこそが、少なくとも帝国西部諸県における「ロシア化」の目標であった。異民族の完全な同化を目指すような大ロシア化は、実現不可能であったばかりでなく、それを長期目標としただけで(唯一の現実的な統治方法である)エスニック・ボナパルティズムに支障が生じるであろうことは自明であったから、望ましい政策でさえなかったのである。
「分割・統治」が帝国支配の本質的属性であったとすれば、「鉄道建設の時代から学校建設の時代へ」といった定式(21) に代表される純クロノロジカルな民族政策の傾向、つまり個々の民族政策(対ポーランド人政策、対フィンランド政策等々)を越えた、ツァーリ政府の一般的民族政策が存在しえたかどうかは疑わしい。というのは、「分割・統治」原則の下では、あるエトノス集団に対する不寛容政策は、その集団と混住する別のエトノス集団への寛容政策と結びつかざるをえない場合が多かったからである。たとえば、ポーランド系地主に打撃を与えるために資本主義以前的な土地法制である地役権が政策的に維持されたとすれば、それは、客観的にはウクライナ人農民を助けていることになる(22)。別の例を挙げれば、1870年代、大ロシア民族主義の高揚に押されて、第二次ポーランド反乱(1863-64)後に西部諸県のポーランド人に課されていた土地取得制限をバルト・ドイツ人にも拡大しようとする提案がなされたが、ヴァルーエフ内相らの抵抗で実現されなかった。なぜなら、バルト・ドイツ人の土地取得を制限すれば、ポーランド人地主が手放さざるを得なくなるであろう土地の潜在的な買い手を失うことになり、したがって地域の脱ポーランド化が妨げられるからである(23)。同様の関係は、ポーランド人とポーランド人でない旧教徒との間にも成り立った。
以上に見たように、現地支配階級の取り込み、樹形的な帝国のコスモロジー、そして「分割・統治」という、ロシア帝国の構造・機能上の三つの特徴は、いずれも程度の差こそあれ「民族の牢獄」論に反省を迫るものである。
2. 右岸ウクライナにおける民族政策の特殊性
前節で見た帝国の構造・機能上の三つの特徴が南西3県にどのように現われたかを考察するにあたって銘記されなければならない特殊事情は、南西地方においては支配階級が主にポーランド人とユダヤ人から構成されており被支配階級が東スラブ族たるウクライナ人から構成されていたという事実である。これが持つ意味を理解するためには、まず、当時の民族名称に関する現代人の誤解を解かなければならない。19世紀のロシア政府の公式の用語法によれば、帝国西部諸県における民族間関係は、〈図2〉のように表わされた(前出の樹形図を前提として、ここでは範疇のみを示す)。
〈図2〉帝国南西3県における民族の呼称・相互関係認識の変遷
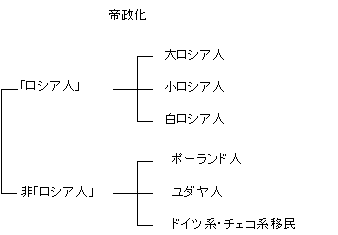 |
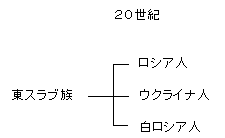 |
「ロシア人」という言葉は、こんにちでいうところの「東スラブ族」という意味で用いられていたのである(これを受けて、本稿では、当時の公式用語法による「ロシア人」を括弧付きで、こんにちの意味におけるロシア人を大ロシア人と表記する)。したがって、当時の用語法における帝国南西地方の「ロシア化(obrusenie)」とは、大ロシア化ではなく、東スラブ化を意味していた。図から容易に推察されるように、その内容は、第一義的には脱ポーランド化、第二義的には脱ユダヤ化、第三義的にはドイツ系・チェコ系移民の同化であった。他方、「現地住民(korennoe mestnoe naselenie)」、つまりこんにちの用語法で言うところのウクライナ人は、当時の公式用語法によればもともと「ロシア人」なのだから、「ロシア化」の対象とはなりえず、もしなったとすれば、それは「数世紀にわたるポロニズムの影響から現地住民を解放する」という文脈においてのみであった。もちろん、東スラブ族全体を単一の民族(narod)とし、ウクライナ人や白ロシア人を独立した民族とみなさないことそのものが大ロシア化政策である、という議論は成り立とう〈補注〉。しかしいずれにせよ、研究者は「ロシア化」という言葉を用いる際に、それが現代的な意味による「ロシア化」なのか、それとも歴史的用語としての「ロシア化」なのかという点を必要に応じて示すべきだろう(たとえば、前者には russifikatsiia、後者には obrusenie という括弧書きを付してはどうだろうか)。
ちなみに、obrusenie そのものが、帝国南西地方における政府史料に頻出した用語ではない。政府は「ロシア的要素を強める」という表現を好んで用いた。客観的にも、これが最も適切な表現である。なぜなら、「ロシア化」という言葉が「強者(大ロシア人)が弱者(被支配民族)を虐める」というニュアンスを含むのに対し、南西3県におけるロシア政府の民族政策は、自分たちが圧倒的に劣勢にあるというコンプレックスの上に成り立っていたからである。このコンプレックスの根拠となっていたのは、人口構成、身分構成、土地と資本の所有、識字率などの社会経済的諸側面においてポーランド人、ユダヤ人が自分たち「ロシア人」に対して優位にあるという認識のみではなかった。むしろ、エスノポリティクスを展開する上での国家理念の成熟度、エトノス集団の結束力、戦略戦術を展開する技量、つまり広義の政治文化において自分たちがポーランド人、ユダヤ人に太刀打ちできるわけがないという認識であった(24)。第二次ポーランド反乱後に西部諸県のポーランド人の土地所有が制限されたのも、彼らの経済基盤一般を殺ごうとしたのではなく、エスノポリティクスを展開するための政治資源としての土地所有が問題とされたからであった(25)。
ポーランド人が頑強に同化を拒み、類稀なる結束力を発揮したことのひとつの理由は、ロシア革命以前のポーランド人が通常の民族学的な意味での民族ではなく、帝国(具体的にはレーチ・ポスポリータ)臣民としての政治的民族であったということである。20世紀に彼らが蒙った苦難に満ちた運命の結果、こんにちのポーランド人は通常の民族学的民族に進化(退化?)してしまい、自分たちがかつて大帝国を建設したという事実を忘却している傾向がある(26) ので、このことは特に強調しておかなければならない。当時、「ポーランド人」とは、特定の民族集団に帰属する者を指したのではなく、カトリックとポーランド語、ポロニズムを受容した者を指したのである。その意味では、当時の「ポーランド人」概念は、ロシア人、アメリカ人といった非民族学的な国民概念に近い。ロシア、ウクライナの史学史において、19世紀のロシア帝国西部諸県のポーランド人の政治活動に対して「民族解放運動」という近代的な名称があてられてきたのは、まことに奇異なことである。実際には、ロシア帝国西部諸県で展開されていたのは抑圧民族と被抑圧民族の間の闘争ではなく、二つの帝国理念・帝国文化の間の闘争であり、たまたまそのとき、一方が勝者、他方が敗者であったにすぎない。まんいちレーチ・ポスポリータがロシア帝国との闘争に勝っていたら、ロシア帝国がポーランド人に対して行なったのと同じことを、ポーランド人は東スラブ族に対して行なっただろう。こうした事情から、「ポーランド民族の独立」という目標とは全く異質の「レーチ・ポスポリータの再興」という目標、民族学的領土ではなく歴史的領土(「バルト海から黒海まで」)の回復という目標は、ロシア帝国領内のポーランド人がポーランド人として踏みとどまるための生命線であり続けたのである。しかも、ポーランド人がロシア帝国西部の支配階級内の多数派を占める限りにおいて、この目標にはある程度の実現可能性があったのである。
第二次ポーランド反乱後、大ロシア側がポーランド人にしばしば示唆したのは、西部諸県に対する野心を捨てよ、そうすればポーランド本土とは同君連合的な関係を復活してあげようということであった(27)。しかし、政治的民族としてのポーランド人にとっては、これは自己同一性の否定にほかならなかった。西部諸県がある限り、ポーランドはフィンランドになるわけにはいかなかったのである。このように、西部諸県のポーランド人が、ポーランド分割以後120年以上にわたって自らの言語と文化を維持できたのは、彼らが「レーチ・ポスポリータの再興」という夢に支えられていたからであるが、まさにこの事情が、ポーランド反乱に代表されるような冒険主義に彼らを駆り立て、彼らの民族政策を硬直化させ、そのうえ、ロシア帝国の他の被支配民族から、大ロシア人と同じ穴の狢として嫌われ仲間外れにされる(28) 原因となったのである。
次に、被支配階級が主に「ロシア人」であったという点であるが、まさにこのために、ロシア政府の西部諸県政策は、東や東南への膨張政策にはない一要因を付与された。それは、「数世紀にわたってポーランド人やユダヤ人に搾取されてきた同胞である『ロシア人』を解放する」という正当化の論理である。この論理は、西への膨張の時点(ポーランド分割時)には見られなかったものだが、第一次ポーランド蜂起(1830)以後、より決定的には、ドミトリー・ビビコフの南西地方長官就任(1837)以後、ロシア政府が採用し始めたものである。
ここで考察しなければならないのは、ポーランド分割によって、ロシア帝国は、それまでの膨張とは明らかに異質な地域に向かって領土を拡大したのに、現地支配階級の帝国支配階級への包摂という伝統的な統合政策を40年以上にわたって(しかも、第一次ポーランド蜂起の後でさえ暫くの間)堅持したのは何故かという問題である。エドワード・サーデンは、これを四点にわたって説明する。第一に、ロシア、ポーランドのエリートの共通の利益であるところの農奴制秩序がフランス革命やコシチューシコ蜂起によって脅かされたので、両民族の支配階級間の同盟を固める必要があった。ナポレオンがワルシャワ公国を興してポーランド再興の夢を部分的に満たしてくれたときでさえ、ポーランド貴族はナポレオンが伝播しかねない革命理念への警戒心を失うことはなかった。第二に、階級構造がロシアと似通ったレーチ・ポスポリータの併合は、「コスモポリタンな地主エリートに支配される多民族国家」というロシア帝国の伝統的性格を強めると考えられた。第三に、18世紀末にロシアがトルコを圧倒してドニエプル川の安全な航行を確保したので、ポーランド地主(特に帝国南西地方の地主)は欧州への穀物輸出のルートとしてバルト海経由ではなく黒海経由を好むようになった。第四に、西・中欧と接し、レーチ・ポスポリータ末期およびワルシャワ公国下で国政改革の実験を積んできたポーランドのエリートは、ロシア帝国の改革に必要なノウハウを提供してくれると考えられた。この点では、シュリャフタは、ピョートル大帝下のバルト・ドイツ人のような役割を果たすと期待されたのである(29)。
しかし、ロシア政府とポーランド人地主との間の蜜月は、ウクライナ人農民にとっては、レーチ・ポスポリータ時代と比べて待遇が一向に改善されないということを意味していた。ビビコフ南西地方長官が執拗に主張して実現した裁判記録の調査(当時、南西地方の司法機関はポーランド人貴族の手中にあったので、総督が裁判記録を調査することさえ容易ではなかった)によれば、ポーランド人貴族・荘園管理人の農奴への暴力による傷害致死事件、妊婦の流産などが、キエフ県だけでもほとんど毎月のように起こっている。しかも加害者の大半は刑事罰を免れており、被害者についてはその氏名さえ記録に残されていない(30)。さもありなんといった話だが、メチスラフ・ポトツキー伯のように、美しい農奴の娘を集めてハーレムのようなものを作った例もある(31)。
ポーランド人貴族の帝国支配階級への包摂という路線にこれほどの慣性力があったとするならば、それが放棄されるや、ロマノフ朝崩壊に至るまで(様々な政策上の揺れはあったものの)再び採用されることがなかったのは何故かということが次の疑問として浮上する。もちろん、ここにおいては第二次ポーランド蜂起が決定的な意義を持ったが、若干の点を付け加えたい。第一は、「現地同胞の解放」という正当化根拠には、領地台帳改革(32) が農奴解放にゆきつかざるをえなかったことに示されるように、一種の自縛作用があったということである。いったん掲げた以上は降ろせない旗であったと言えよう。
第二に、レーチ・ポスポリータと対峙していたとき以来、大ロシア人側は、レーチ・ポスポリータの東の辺境は「ロシアの固有の領土」、小ロシア人や白ロシア人は「ロシア人」であるという主張を表向きはしてきたが、本音のところでは、ポーランド分割により他人の領土・国民を略取したと考えてきた。ところが、19世紀の中葉から後半にかけて、南西地方長官に後押しされた帝国地理協会南西支部や歴史学におけるキエフ学派のイニシアチブにより、右岸ウクライナにおいて空前の規模で地理調査・民俗学調査が組織された。その結果、ウクライナ民衆が、2世紀以上に及んだレーチ・ポスポリータ支配にもかかわらず東スラブ的な特徴を保っていることが明らかになり、そのおかげで、帝国西部諸県は「ロシアの固有の領土」、「ロシア人」同胞を解放せよといったスローガンが案外科学的な根拠を持っていたことが明らかとなったのである(33)。この時代は、ロシア帝国にとって、ピョートル・セミョーノフやパラディウスらの活躍による地理上の発見の時代であったが、大ロシア人にとって燈台下暗しであった右岸ウクライナもまた「発見」されたのである。
以上のような事情から、ビビコフ総督以降、右岸ウクライナの政府権力はウクライナ人農民に同情的な政策をとった。右岸ウクライナの農奴解放は、それに先行する領地台帳改革と結合され、帝国では例外的に農民の利益を優先して行なわれた。解放後も、ウクライナ農民は、ポーランド人地主の犠牲において多くの土地を獲得した。にもかかわらず、右岸ウクライナでは農民の騒擾の頻度は左岸や南ウクライナよりもずっと多かった(34)。その一因は、政府の農民甘やかし政策である。19世紀末になると、極端な反ポーランド人政策(その反面としての農民甘やかし政策)が大ロシア人地主の南西地方への入植をも妨げていることが自覚され、西部諸県への通常統治の導入(ゼムストヴォ、ゼムスキー・ナチャーリニク制の導入、その反面では地役権の廃止)と結合してポーランド系貴族を再び帝国支配階級として組み込む道が模索されるようになった(35)。しかし、これはロシア帝国の西部諸県支配の正当性の根幹に関わる問題であったから、政策転換は容易ではなかった。しかも1905年革命の際に、南西地方のポーランド人貴族が「歴史的領土」回復の野望を捨てていないことが示されたので、革命後は政府の対ポーランド人政策は再び硬化した。そのうえ国会開設により、ウクライナ人の票を大ロシア主義政党に惹きつけるためのポピュリズムが強化されるに至り、結局、ポーランド人貴族の再包摂政策は本格化しなかったのである。
ここで、現地住民「解放」論の具体例を、1911年度のヴォルィニ県知事の恭順報告書 (vsepoddanneishii otchet) に見てみよう。知事は、県の商工業資本のほとんどがユダヤ人の手中にあり、しかもその状況が変わる兆しさえないことを次のように説明した。「その原因は、現地住民[ウクライナ人 ム 著者]の文化の低さ、彼らのユダヤ人への物質的従属、そして、主要には、全スラブ人に固有の…無気力(inertnost')である」。この状況を変えるためには、「ユダヤ人の搾取と闘うための強力な武器を与えてくれるであろう」学校網を整備しなければならない。南西地方において学校がこのような役割を期待される以上、ゼムストヴォ学校ではだめで、あくまで政府学校を増設してゆかなければならない。そしてこれらの学校は一般的な教育を行なうだけでは足りず、「(現地住民を)取り囲む異族(36) との闘いを勝利に導くような実践的な生きた知識」を与えなければならない(37)。一見して明らかなように、この報告においては、学校建設というそれ自体は進歩的な事業が、南西地方の「ロシア化」=脱ユダヤ化の課題と結び付けられている。同じことが、協同組合政策や酒類専売政策にも言えた。前者について敷衍すれば、内地諸県においては協同組合運動は主にゼムストヴォの援助を受けて発展し、県知事権力はそれを潜在的左翼運動とみなして、どちらかと言えば警戒的だったのだが、南西地方の総督や県知事は、「協同組合はユダヤ人の搾取と闘う武器として重要である、何故、我が県のゼムストヴォ(1911年以前は地方経営委員会)はこれをもっと熱心に援助しないのか」と発破をかけるのが常だった。ロシアの協同組合活動家にとっても、南西地方の総督、県知事は協同組合に甘いというのは周知の事実であり、たとえば1913年の全露協同組合大会がキエフで開かれたのもこのためだった(南西地方以外では、このような大会開催の許可はおりなかっただろう)。ただし、この大会で「北派」(大ロシア派)と「南派」(ウクライナ派)の路線争いが浮上し、ウクライナの協同組合が分離主義的な色合いを持つことが明らかになって(38) 以降は、南西地方の政府権力は協同組合への態度をやや硬化させたようだが、それでも内地諸県よりは寛容だったと言える。
総じて、南西地方におけるビビコフ以降の政府の民族政策の基本は、「現地民(ウクライナ人)と新教徒(ドイツ人・チェコ人)を味方につけて、ポーランド人とユダヤ人を叩く」というものとなった。言い換えれば、エスニック・ボナパルティズムが一切の原則なしに展開されていたわけではなかったのである。
なお、チェコ人がここで「新教徒」のカテゴリーに加えられているのは奇異に思われるかもしれない。次節で述べるように、たとえばヴォルィニ県のチェコ語使用住民の26.6%は旧教徒だったからである。どうやら、「正教徒『ロシア人』と新教徒」という範疇は、実態を反映するものとしてよりも、西部諸県においてポーランド人とユダヤ人に対置さるべき規範的・人工的な範疇として機能していたようである。北西地方に至っては、リトアニア・タタールまでがこの範疇に含められていた(39)。いずれにせよ、ドイツ人、チェコ人の入植・優遇政策は、南西諸県に進んだ中欧農業技術を伝播させることと並んで、現地ポーランド人の勢力を殺ぐことをも目的としていた(40)。しかし、ドイツ人、チェコ人の立場は露墺関係の悪化と共に悪くなり、その居住・土地所有に対する制限措置がとられるようになったのである。
以上から明らかなように、右岸ウクライナにおける帝政の民族政策は、レーチ・ポスポリータの遺産としてのポーランド人とユダヤ人の優位の克服、それらに搾取される現地「ロシア人」の解放を基本モチーフとした。ポーランド文明およびユダヤ文明・対・ロシア文明という対抗軸を前にしては、「大ロシア人・対・ウクライナ人」という軸は二義的な意味しか持たなかった。それどころか、19世紀中葉に活躍したウクライノフィルの第一世代 (stara hromada) は、「ポロニズムと闘うためには、ロシア人(東スラブ族)は団結しなければならない。そのためにも、大ロシア人は小ロシア人に対する尊大な態度を改めるべきだ」という論法をしばしば用いたのである。つまり、「二重のアイデンティティー」(マロルースィであると同時に「ロシア人」である)を認める点で、帝政とウクライノフィルは同じ土俵に立っていたのである。このような穏健路線の成功例は、1870年代初頭、やがてウクライノフィルの合法的な組織媒体となる帝国地理協会南西支部が、南西地方長官の庇護下で開設されたことであった。当時の南西地方長官ドンドゥコフ-コルサコフは、ウクライノフィル運動を取り込むことによって、右岸ウクライナのポーランド人の勢力を殺ごうとしたのである(41)。
本節をまとめる。帝政下の右岸ウクライナにおいては、「ロシア人」に対するポーランド人、ユダヤ人の優位があまりに極端で、しかも彼らに支配・搾取されていたのが「ロシア人」(ウクライナ人)であったという特殊事情から、ロシア帝国の構造・機能の三要素(現地支配階級の取り込み、樹形的コスモロジー、「分割・統治」)はストレートな形では発現しなかった。まず、現地支配階級たるポーランド人の帝国支配階級への包摂政策は、第一次ポーランド反乱ののち部分的に、第二次反乱ののち決定的に、放棄されざるをえなかった。また、被支配階級たる「ロシア人」を解放するというポピュリスト的な正当化根拠が民族政策の根幹に置かれたため、「分割・統治」政策も十分に柔軟な形では展開されえなかったのである。ただし、頗る機能主義的な伝統的帝国政策が適用できなかったために、かえって、土地問題のポピュリスト的利用や大ロシア主義政党の育成のような現代的な民族統合政策が発達したことは指摘さるべきである。
〈補注〉そもそも、ルーシ人(ウクライナ人)が「ロシア人」とは別のエトノス(narod)なのか、それとも、東スラブ族は単一のエトノスでありマロルースィはその分岐にしかすぎないのかというイデオロギー闘争は、モスクワ国家とレーチ・ポスポリータの間で、当事者であるウクライナ人の頭越しに(ウクライナ民族運動が生まれるはるか以前に)発生したものである。「ルーシ人は『ロシア人』とは別」という主張は、レーチ・ポスポリータがウクライナを植民地化するためのイデオロギーであり、「マロルースィは『ロシア人』の一分岐」という主張は、ロシアがウクライナをレーチ・ポスポリータから奪回する(あるいは奪う)ためのイデオロギーだったのである。
また、ツァーリ政府の言語政策も、上述の民族観と類似した、次のような論理構造を有していた。 (1)「ロシア語」は単一の言語であり、その中に大ロシア方言(narechie)、小ロシア方言、白ロシア方言が存在するにすぎない、大ロシア方言が「ロシア語」内の標準語の地位を占めている以上、小ロシア人、白ロシア人もこれを修得し、公共の場では用いるべきである。ここにおいて大ロシア方言が果たす役割は、近代フランス語、イタリア語が成立する過程でイル・ド・フランス方言、トスカナ方言が果たした役割と同様である。(2) 小ロシア方言はポロニズムに汚染された「ロシア語」なので、大ポーランド主義との闘争という南西地方の「ロシア人」に課せられた歴史的課題を妨げる方向で作用する。まさに南西地方においてこそ、標準語としての大ロシア方言は重要な役割を果たしてきたのである。サムイル・ミスラフスキーからゴーゴリに至る、18世紀から19世紀初頭にかけての大ロシア語の確立者たちの多くがこの地から輩出されたのは偶然ではない(42)。
このように、東スラブ人(語)の一体性の強調、ポロニズムとの闘争の必要性からその一体性を正当化するという二点において、ロシア政府の民族政策と言語政策はパラレルな関係にあったのである。
次章へ
45号の目次へ戻る