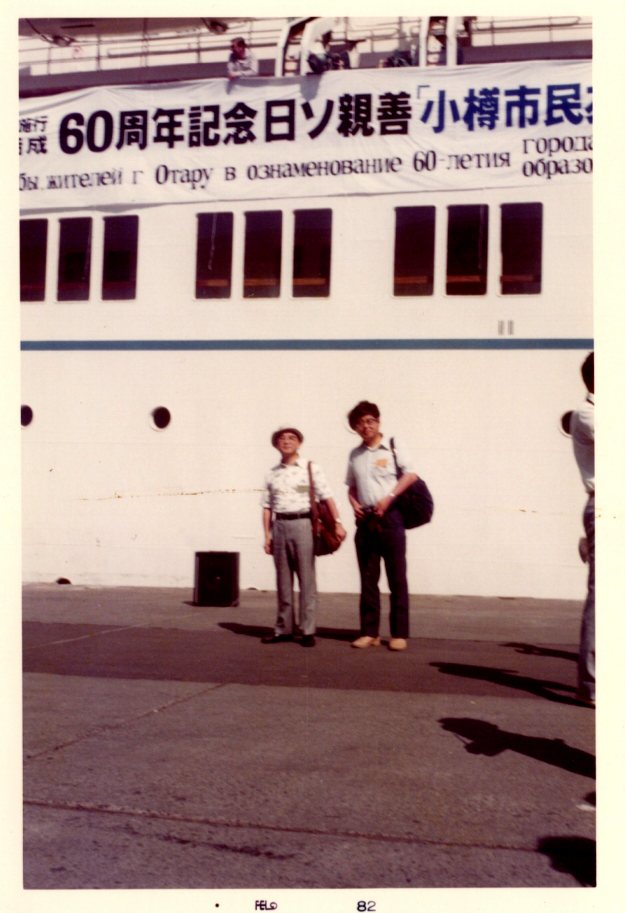ニュース
- センターニュース
- 英文センターニュース
- 研究員の仕事の前線
- INCSA2026 日本サテライト会議 発表募集のお知らせ
(2026年2月20日) - FVFP教員のメディア出演
(2025年12月8日) - 19世紀研究の国際ネットワークのご案内
(2025年6月23日) - 【新刊】望月哲男名誉教授の新著 Микрокосмы Достоевского 刊行
(2025年6月20日) -
追悼:外川継男先生
外川継男先生とSRC
外川継男先生を偲んで
外川継男先生著作一覧
(2025年4月23日) - ミルラン・ベクトゥルスノフ特任助教がAb Imperio最優秀論文賞を受賞
(2025年4月21日) - ロシアのウクライナ侵攻特集
- INCSA2026 日本サテライト会議 発表募集のお知らせ
- スラブ研究センター・レポート
研究員の仕事の前線
追悼:外川継男先生
センターの発展の礎を築くうえで、組織面でも国際研究交流の面でも顕著な功労のあった外川継男先生の追悼文を、元文学研究科長の栗生澤猛夫先生に書いていただきました。
外川継男先生を偲んで
栗生澤猛夫(北海道大学名誉教授)
本2025年1月3日、外川継男先生が虚血性心不全のため亡くなられた。満91歳の誕生日を迎えられる3日前のことであった。
先生は上智大学を退職された後、2度も癌手術をされた。ご令室郁子様をはじめ周りは皆心配したが、その後も十数年は、夏の間札幌で過ごされ、私などもその都度お目にかかったので、お元気になられたことを喜んでいた。ご子息、健一氏によれば、晩年の先生は「散策を楽しみ、川辺のベンチで鳥のさえずりを耳にしたり、大好きな本屋で至福の時を過ごしたり」の、また家庭でも「穏やかで笑いの絶えない」のんびりとした生活であったという。
私が外川先生に最初にお目にかかったのは1971年のことである。その年の春、私は一橋大学大学院修士課程を修了し、北海道大学文学研究科博士課程に進学、鳥山成人教授の指導を仰ぐべく札幌の地に足を踏み入れた。そのとき、すでにゲルツェンの『向こう岸から』の邦訳で有名であった外川先生にすっかりお世話になった。会ったこともない一介の院生に対し、先生は、引っ越し荷物(布団と若干の衣類、それにダンボール30箱ほどの本)を、当時のスラブ研究施設のご自身の研究室宛てに送ることをお許しになったのである。これがお世話になった最初である。私はそのとき施設のことも、そこで先生がどのような役職についておられるのかも、よく知らなかった。正直なところ、そのようなことには頭が回らなかった。先生ご自身が東京大学文学部(西洋史)を卒業された後、北大文学研究科大学院に進学されたご経験から、頼る者のない貧乏院生にとって、所属先を変えることや引っ越しがいかに大変であるかを理解されておられたのだと思う。当時の施設は小なりとはいえ(専任研究員はおそらく3名だけであった)、先生はすでに施設長をなされていたが、私がそれを知ったのは、大分後になってからのことである。
スラブ研究施設はその後、1978年にセンターとなり(先生が初代センター長に就任された)、目覚ましい発展を遂げることになるが、万事につけ感度の鈍い私にとっては、いわば草創期の牧歌的なスラブは理想的な居場所であり、その時代の先生はたいへんありがたい指導者であったように思う。先生はその段階ですでにアメリカ、フランスへの留学を果たされており、ロシア語はもとより英仏語も自在な研究者として、我々のよき先達であられたのである。私が北大院生になった翌年には、ポーランドがご専門のドイツ帰りの伊東孝之先生も助教授として赴任され、我々院生(当時のスラブは研究施設であり、固有の院生はいなかったが)にとっては、この両先生は巨大な、しかしお二人のお人柄ゆえに適度な、刺激的存在であった。私などが潰れもせずに、研究は楽しいと思いながら続けられたのは、草創期スラブの先生方のおかげであったと言って過言ではない。
外川先生のお仕事で、このころ私がもっとも刺激を受けたのは、上記ゲルツェンの『向こう岸から』もそうであったが、なによりもチャアダーエフの「哲学書簡」のご翻訳であった(『スラヴ研究』6–9号、1962–65年)。フランス語原文から訳された第一書簡(第二~第八書簡は当時まだ露語訳しか刊行されておらず、先生も露語から和訳された)の次のような文言、すなわち、ロシアは「過去も未来もなしに、完全な停滞の中にあった」、「我々[ロシア人]は人類全体の一部を構成するというよりも、世界に大きな教訓を与えるためだけに存在する」、「ヨーロッパのすべての民族は、時代のなかを手に手を携えて進んできた……、我が国においては全人類的教育を新たに始めなければならない」などは、私に「ロシアとヨーロッパ」というテーマの重大性を改めて認識させるものであり、ロシアにはそもそも「歴史」がないとするチャアダーエフの慨嘆は、私にとってもまさに「闇夜にひびいた一発の銃声」のようであったのである。
先生はそのころゲルツェンを中心にツルゲーネフやバクーニンのことを研究対象にされていたが、それは論文「二つの論争」に結実し(『スラヴ研究』15、17号、1971年、73年)、さらに同1973年に、御茶ノ水書房から単行本『ゲルツェンとロシア社会』として刊行された。いつのことであったか、先生は我々院生のためのいわば私的外川ゼミで(その終了後にどこか居酒屋へ行くのが楽しみであった)、ゲルツェンがツルゲーネフとの論争を通してロシア農民とその共同体の重要性に目覚め、それが「ロシア的社会主義」理論の構築につながったと、話されたのであった。
これと並行して左近毅さんと共に編まれた『バクーニン著作集』(全六冊、白水社、1973–74年)も忘れ難い。私も短編のいくつかを翻訳するよう求められたが、先生ご自身が「鞭のゲルマン帝国と社会革命」、「マルクスとの個人的関係」、「革命家の教理問答書」、「ドイツと国家共産主義」などの大部の論文を訳出された。先生がまだ30歳代後半のお仕事で、施設の運営管理をこなしながらの、精力的な研究活動には圧倒される思いであった。
先生はその後1978年に『ロシアとソ連邦』(講談社版『世界の歴史18』)を出版された。40歳代前半のお仕事で、通史というのは、個別研究を究め老境に入った大家のなしうる仕事と思っていた私にとっては、いささか衝撃であった。しかしながら外川版「ロシア史」は、ロシアとその歴史が日本人にとってもつ意味についての深い洞察に満ちており、バランスのとれた構成と読みやすさもあって、日本の多くの読者に歓迎されたのであった。本書において先生は、まず序章で「ロシアと日本の近代化」の類似点、相違点について考察した後、近代の章で「ピョートルと日本」、「エカテリーナと大黒屋光太夫」を、さらに19世紀末から20世紀にかけての箇所では、「ロシアの極東進出」(最初の訪日使節レザーノフ、ゴロヴニンと高田屋嘉兵衛、プチャーチン、日露和親条約、千島・樺太交換条約)、「日露戦争と1905年革命」を取り上げ、引き続きロシア革命後の「日本のシベリア出兵」を概観した後、最終章を「第二次世界大戦後の日ソ関係と北方領土問題」にあてて本書全体を締めくくられたのである。まさに日本人のためのロシア史を先生は物されたのであった。後に先生ご自身が記されているところによると、先生の東大時代の恩師、西洋古典古代史の権威村川堅太郎教授がこれを読み、すべての頁に書き込みまでしていたという(「ある歴史学者の死」1992年、『サビタの花』2007年所収)。
その後の先生の研究対象は、次第にロシア近代史プロパーから日露関係史へと移っていったが、その萌芽はすでに上記『ロシアとソ連邦』に明瞭に現れていたのである。先生のご関心のこの分野への移動は、ちょうど先生が施設のセンター昇格の大仕事を終えられ、センター長の職も他の方々に譲られて、上智大学へ移られていくのと時期的に重なっていたように思う。私は日露関係史研究の必要性を十分理解しているつもりではあるが、自分の能力からして、そこまで広げることはできないと観念していたので、正直言って、この面での先生のお仕事を手に取ることはあまりなかった。ただ先生の「日露・日ソ関係の特徴」(『日露200年』所収、1993年)は別である。これはいかにも先生らしい講演で、私は何か蒙を啓かれたような気がしたのである。
先生はこの講演において、両国関係の特徴を三点指摘している。その第一の特徴として先生があげられたのは、両国の長い確執の歴史において、被害をこうむった人々(千島アイヌや中国、朝鮮半島の住民)が多数いたことである。これをまずもって認識しておく必要があることを先生は力説されたのである。通常国家間の関係の問題においては、国際関係や地政学的要因が主に取り上げられ、政治や経済、軍事に焦点が合わされるが、その重要性を十分に認識されながらも、先生はあくまでもそこに居住する人々のことを忘れてはならないと説いたのである。人間的アプローチを選ばれたと言ってよいと思う。先生のあげる第二の特徴も興味深い。両国間のコミュニケーション技術がきわめて貧弱であるという事実である。両国が長い関係のなかで、常に行き違いや誤解に悩まされてきたことが指摘される。言語や文学、文化の地道な研究・教育の重要性を先生は誰よりも強く認識されていた。第三は、両国間の関係には常に第三国が強い影響を与え、また介入したことである。最初期(江戸時代)はオランダであり、次に英国(18世紀後半から19世紀)、そして現代においては米国である。日本人は多くの場合、これらの国々の眼鏡を通してロシアを見てきたというのである。私は日本におけるロシア史研究が(といっても私の場合、中近世史に限定されるが)、これまで、通常は意識することなく、米国やヨーロッパ諸国、とりわけドイツのそれの強い影響下にあったと思っている。これを「バイアス」として認識しない限り、我々の研究には偏りが生じざるを得ない。これを避けるため私は可能な限り視野を広く保ち、「事実」に即した研究を志ざしているが(もっともそれが容易でないことは言うまでもない)、これは外川先生の姿勢に通じるものがあると知って、心強く感じたのであった。先生の両国関係史に対する見方はあくまでも人間中心的であったように思う。
晩年の先生の主要な研究対象は、とくにラーゲリ(公式的には矯正労働収容所、実際は強制収容所といってよい)体験者フランス人ジャック・ロッシ氏と深く結びついている。コミンテルンの活動家であったロッシ氏は、1937年(本人が28歳の時)にモスクワに召喚、逮捕され、そのまま21年間もラーゲリに入れられていたが、「釈放」後も自由の身となったわけではなく、様々な苦労を重ねた後の1985年に(本人76歳のとき)ようやく、フランスに戻ることができたという。先生は、ロッシ氏といわばラーゲリ仲間であった内藤操上智大学教授(前北大教授、ペンネーム内村剛介氏)の仲介でその知己を得て、彼のラーゲリ体験記などの紹介に取り組まれることになったのである。
その最初が、ロッシ著『さまざまな生の断片』(成文社、1996年)の翻訳である。これは「ソ連強制収容所の20年」と副題にあるように、収容所での過酷な体験を約50のエピソードとして綴ったものである。先生は、自己の体験を悲劇として誇大に描いたり、ソ連当局の非人間的扱いを声高に糾弾したりすることのまったくない著者の人柄に大いに打たれたようである。先生のロッシ氏紹介の次の仕事は、2004年の『ラーゲリのフランス人』(恵雅堂、サルドとの共著)の翻訳である。これは3部全35章からなる大部の自伝で、その第二部(全24章)が収容所生活の記述に宛てられている。
ロッシ氏のこれらの著作は、1997年に恵雅堂から出たその『ラーゲリ(強制収容所)註解事典』(内村剛介監修、梶浦智吉、麻田恭一訳)とともに、それまで我々がソルジェニーツィンやギンズブルグ(『明るい夜、暗い昼』)、シャラーモフ(『コルィマ物語』)などから得てきた、ソヴィエトの強制収容所の実態とソヴィエト社会そのものの在り方に関する知識を、大幅に補充、増進させるものであった。外川先生の晩年のお仕事の意義はきわめて大きいと言わなければならない。
これとの関連で、先生がその間に取り組まれたヴェルト「人民に敵対する国家」の紹介も重要である。これはクルトワ編の『共産党黒書』(全五部)の第一部「ソ連篇」の翻訳で、2001年にこれも恵雅堂から出版された(その後2016年にちくま学芸文庫に入る)。これはフランス歴史学のよき伝統の上に立つニコラ・ヴェルトが、ソヴィエト社会の根底にある「暴力」という事象の展開の全史を、丁寧にたどった大論文で(仏語原文250頁)、一つのすぐれたソヴィエト・ロシア史論と言って過言でない。先生は当初これを翻訳することをためらったようである。内容の深刻さと大部の著作であることが大きな要因と推測される。しかしロッシ氏がこれを推薦してきたこともあって、最終的には相当の覚悟をもってこれに取り組まれた。糖尿病に起因する体の不調と戦いながら完成されたと伺っている。先生は「解説」のなかで、ナチズムと共産主義とを区別せずに論じる編者クルトワのいささか乱暴なソヴィエト論に批判を加えつつ、ヴェルトの研究を高く評価しているが、先生のこの立場には私も大いに賛同したところであった。
さて本拙文の冒頭に、私が最初に先生にお世話になった時のことを書いた。しかしいうまでもなくそれだけであったわけではない。そこでlast but not least、その他の忘れてならないことについても、最後に思いつくままに記しておきたい。
私は進学してすぐに、生まれてはじめて激しい目の痛みに悩まされた。私は中学の時以来眼鏡を着用しており、視力の低下には常に悩まされていたが、痛みに見舞われたのはこの時が初めてであった。進学したばかりなのに、一時は研究の断念と退学を考えた。それを知った先生は、その場で大学病院に電話をかけて下さり、私は治療を受けることができた。痛みの原因は特定されず、したがって有効な治療法もみつからず、その後も10年ほどは痛みと付き合うことを余儀なくされたが、原因不明ということは、とくに深刻な病気でもないと知っただけで、随分と救われた気分になった。先生はまた何度も私(ども)をお宅に招いてくださり(いやむしろこちらから押しかけたと言った方が正確かもしれない)、そのたびに奥様の手料理をごちそうになった。今にして思えば、あまりに無遠慮だったと汗顔の至りである。先生と奥様、お子様方にはお赦しを請う以外にない。拙宅を建てる時も、先生がお口添えをしてくださった。栗生澤さん、家というものは傾かずにまっすぐ立っていれば、よしというぐらいの気持ちでいた方がいいですよ、と引き渡しの時に先生がおっしゃったことをよく覚えている。そのほか、私が1974年にドイツへ留学する際には、業績(わずかしかなかった)と履歴書を置いていくように言ってくださった。公募があれば、出すこともできるかもしれないというのである。私はそのおかげで、留学後時を置かずに小樽商科大学に赴任することができたのであった。その意味でも先生は掛け値なしに私の恩人であった。御礼の言葉もない。
外川先生、安らかにお休みください。ありがとうございました。