沿革と概要
研究活動
ス
ラブ・ユーラシアの変動:自存と共存の条件
重点領域研究(1995〜1997年度)
スラブ研究センターが中心となって組織した「スラブ・ユーラシアの変動-自存と共存の条件-」(1995−1997年度)は、ソ連邦と共産党体制の崩壊、東欧革命、民族紛争の激化、東西冷戦構造の終演など未曾有の歴史的大変動を経験した、スラブ・ユーラシア地域という巨大な空間が変動前と後でどのような異なる性格を持ち、そして今後各国家・民族・社会の自存・共存のためにどのような条件と可能性を持っているかを見極めることを主要な課題としました。研究は3つの柱、つまり、「政治」(政治システムの変革と地域間関係)、「経済」(経済システムの転換と新経済圏の形成)、「文化・民族」(社会変動と自己認識)からなり、それぞれの専門的な視点から変動の諸様相(実態・意味・影響・将来の方向性など)を分析しました。
ウエブサイトURL
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/juten/juten.html
ユ
ーラシア地域大国の比較研究
新学術領域研究新学術領域研究(2008〜2012年度)
新学術領域研究とは2008年度に始まった文部科学省の科学研究費補助金です。スラブ研究センターが中心となって組織した「ユーラシア地域大国の比較研究」(2008−2012年度)は、超大国とその他の国々との間に地域大国(ロシア、中国、インドなど)という中間項を挿入することで、世界を理解するうえでの新しい視座を確立し、現代世界の様々な問題を検討することを目指しました。国際関係、政治、経済、歴史、社会、文化の6つの計画研究班を作り、それぞれにロシア・中国・インドの研究者を配置しました。研究成果として『シリーズ・ユーラシア地域大国論』が刊行されています。
 ウエブサイトURL
ウエブサイトURL
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/rp/index.html
ス
ラブ・ユーラシア学の構築:中域圏の形成と地球化
21世紀COEプログラム(2003〜2007年度)
21世紀COEプログラムは、「大学の構造改革の方針」に基づき、2002年から文部科学省の事業(研究拠点形成費等補助金)として措置されたものです。日本におけるスラブ地域研究をリードしてきたセンターが中心となって組織した「スラブ・ユーラシア学の構築:中域圏の形成と地球化」(2003-2007年度)は、従来の固定した地理的な境界による線引きによって地域を設定するのではなく、内的、外的、時間的な要因を考慮した柔軟な地域設定を行い、それにより変動しつつある地域の現実をとらえようとする試みでした。スラブ地域およびそれ以外の地域の研究者との連携や交流が促進され、ネットワークが構築され、「地域大国」や「境界研究」という新しい研究方法概念が生まれました。
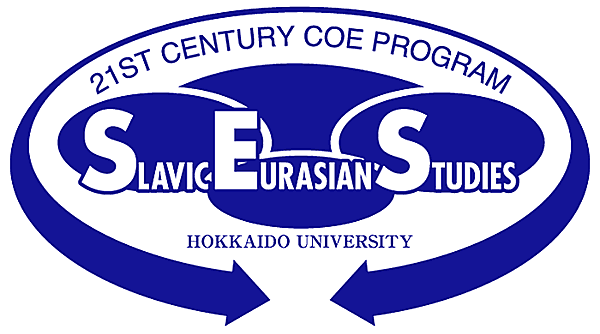 ウエブサイトURL
ウエブサイトURL
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/rp/index.html
境
界研究の拠点形成:スラブ・ユーラシアの世界
GCOEプログラム(2009〜2013年度)
GCOEとは、国際競争力ある大学づくり・研究者育成を図るために2007年度に始まった文部科学省のプログラム事業です。スラブ研究センターが中心となって組織した「境界研究の拠点形成:スラブ・ユーラシアの世界」(2009-2013年度)は、今日、ユーラシア各地で国境問題、文化摩擦といった形で、生じている境界をめぐる対立・紛争を実態・表象の双方から考察し、境界問題を読み解くための新しい研究領域・拠点を確立することを目指しました。また、「境界研究」教育講座を開設し内外の受講者に修了書を発行するとともに、博物館展示、政策提言を通じて得られた成果を広く社会に還元しました。
 ウエブサイトURL
ウエブサイトURL
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/BorderStudies/
国
際シンポジウム
センターでは、通常年2回、夏と冬に国際シンポジウムが開催されています。これには世界中から100名を超える第一線の研究者や専門家が参集し、センターにとって中心的な行事の1つとなっています。シンポジウムの成果は報告集などの形で逐次出版されています。シンポジウム開催にあたっては報告論文が事前に提出され、それがホームページからダウンロードできるようになっており、討論重視がセンターのシンポジウムの大きな特徴となっています。下記は、2012年から2017年までに開催された国際シンポジウムの題名です。 このほかにも、内外の講師を招いて様々な研究会やセミナーが随時開催されています。
過去の国際シンポジウム
2024年度/冬/ スラブ世界における言語・ネイション・標準化:その類似と相違
2024年度/夏/ The Crucible of a New World? Russia’s Borderlands at the Dawn of the Twentieth Century
2023年度/冬/ Borders, Boundaries and War across Eurasia: Cycles of Violence and Resilience
2023年度/夏/ 崩壊の局面:アフロ・ユーラシアから「14世紀の危機」を思考する
2022年度/冬/ ウクライナとロシアの生存戦略:開戦から1年を迎えて
Above the Permafrost: How Climate Change and Resource Development are Changing Local Life in the Arctic
2022年度/夏/ アナーキスト的転回?長い20世紀における帝国支配と抵抗
2021年度/冬/ 権威主義的統治の制度と戦略
2021年度/夏/ 不確実性の時代のスラブ・ユーラシア研究:対話と再検討
2020年度/冬/ 帝政ロシアの地方再訪:文学的想像力と地政学
2020年度/夏/ 北東アジア~ 歴史と未来・発展と摩擦
2019年度/冬/ 帝政ロシアの地方再訪:文学的想像力と地政学
2019年度/夏/ 民主主義の世界的危機? 権威主義とポピュリズムの台頭と進化
2018年度/冬/ 帝国・ブロック・連邦にそびえる言語 1918-2018
2018年度/夏/ 移りゆく北極域と先住民社会 ― 土地・水・氷
2017年度/冬/ ロシア革命と長い20世紀
2017年度/夏/ 中国とロシア・北東アジアの断層線:百年にわたる競争的協力
2016年度/冬/ 体制転換から四半世紀:ポスト共産主義社会の多様化を再考する
2016年度/夏/ ロシア極北: 競合するフロンティア
2015年度/冬/ スラブ・ユーラシア研究センター設立60周年記念シンポジウム 「歴史と記憶の間—世代を越えて考える—」
2015年度/夏/ ロシアとグローバルヒストリー
研
究員セミナー
センターの研究員は、専任・非常勤を問わず、年に1度、研究成果をセミナーで発表することになっています。 セミナーの対象となるペーパーは事前配布が義務づけられ、外部から招聘した専門家による評価を受けます。また専任研究員はそれぞれの専門から対象とされたペーパーに対してコメントを行うことが要求されています。 研究員セミナーは、センターのユニークな自己点検の場であるだけでなく、学際的な地域研究を目指すセンターにとって重要な機能を担っています。
境
界研究ユニット UBRJ (2013年度〜)
界研究ユニットは、2013年4月に設立されたスラブ・ユーラシア研究センターを事務局とする本学での境界研究を推進するための研究ユニットです。メンバーにはセンターの教員だけでなく、文系各部局で境界研究に取り組んでいる教員が名を連ねています。UBRJは、GCOEプログラム「境界研究の拠点形成」終了後の我が国での境界研究の牽引役となっており、さらにはアジアや欧米の境界研究コミュニティとのハブとしての役割も担っています。
 ウエブサイトURL
ウエブサイトURL
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/ubrj/